154 「ドリアン・グレイの画像」 オスカー・ワイルド 西村孝次訳 岩波文庫 画家バジルのモデルになったドリアン・グレイは美青年。彼はヘンリー卿の影響で、美と若さこそが至高であると考え、自分の代わりに肖像画が歳をとればよいと望む。芸術よりも愛が重要だと主張する恋人を自殺に追い込み、ヘンリー卿の誘惑に負けて悪事の限りを尽くす。しかし彼は老けることなく美しいままで、代わりにバジルの描いたドリアンの肖像画が歳をとって醜くなってゆく。ついに人生をやり直そうと決意したドリアンが自らの悪事の証拠である肖像画にナイフを突き立てると、肖像画は元の美しい状態に戻り、ドリアンは老いた醜い姿となって死ぬ・・・。  Oscar Wilde ワイルドの書くものに荒唐無稽はつきものですが、それはもっぱらヴィクトリア朝の社会を舞台にした偶然の出来事ばかり。これはワイルドにしてはめずらしい虚構性要素の強い小説です。多くの場合、この小説はモラリスティックな寓話とか、芸術至上主義と宗教感情の相克を描いたもの、そこに世紀末頽廃と怪奇趣味を加味したものと受け取られてきました。 ヴィクトリア朝ですからね、プロテスタントによる道徳と勤勉の時代ですよ。裏を返せば、抑圧の時代。これに反旗を翻したのが、たとえばこの「ドリアン・グレイの画像」であったわけです。 「ドリアン・グレイの画像」はアメリカの雑誌掲載時に、同性愛が示唆されているとして、たいへんな悪評を被っています。じっさい、1895年の、ワイルドの猥褻行為に対する裁判では、その審理でワイルドを貶めるために雑誌掲載版が法廷で取りあげられて、裁判の結果はみなさまもご存知のとおり、有罪で2年間の懲役刑です。 じつは雑誌に掲載されたものは既に編集者による改訂が施されていたのですが、単行本にするとき、ワイルドはこれに再度手を入れて、若干弁解めいた序文まで付しています。この改訂は可能な限り同性愛に関わる描写を修正したもの。もっともドリアン、バジル、ヘンリー卿の同性愛的な交流、とりわけバジルのドリアンへの同性愛を根本から否定してしまっては物語自体が成り立ちませんから、そこはプラトニックな感情と読めるようにするなどといった配慮もあります。ここでヴィクトリア朝という抑圧の時代の、その偽善ぶりも指摘しておかなければ片手落ちというものでしょう。呆れたことに、「人間的魅力」personalityとか「友情」friendshipなんてことばも、同性愛を連想させる「暗号」と受け取られていたんですよ。ちなみに決定版たる単行本ですが、売れ行きは芳しくなかったものの、酷評されることもなかったようです。 忘れてならないのは、ヘンリー卿によって語られているウォルター・ペイター流の唯美主義。これ、ウォルター・ペイター自身は、唯美主義「運動」なんて意識は持っていなかったみたいなんですね。だからマニフェストらしきものがあるわけでもなかった。その哲学を作品にしてあらわした最初のものが、この「ドリアン・グレイの画像」なんですよ。 前半は普通の文学形式をとっているんです。その中に、いかにもなウォルター・ペイター流の世紀末頽廃の唯美主義が色濃くあらわれている。ところが後半になると、妙に幻想味を帯びてくることになる。そもそもstoryの骨格は、悪魔との契約と破滅、そこに至るまでは二重人格、あるいはドッペルゲンガーの風味で装飾されています。よく言われることに、スティーヴンソンの「ジキル博士とハイド氏」と同じなんです。さらに挙げれば、悪魔との契約はゲーテの「ファウスト」とかマチューリンの「放浪者メルモス」だし、二重人格、ドッペルゲンガーという点では、上記スティーヴンソンのほかに、ポオの「ウィリアム・ウィルソン」の木魂(エコー)も見て取れる。ラストなんかそのままと言ってもいいくらい。 唯美主義マニフェストとしては前半だけで十分。人生の方が芸術を模倣していくのだとする哲学に、大方の善男善女が非難を浴びせ、一方で喝采を贈る人たちもいた・・・過激なマニフェストなんてそんなもんです。それが後半に至って怪奇幻想の風合いを帯びていかなければならなかったのはなぜか。イギリス人はもともと怪談とか幽霊譚が好きだから? 世紀末の心霊主義の流行の影響? それもあるかもしれません。でも私は、ここにプロテスタントに対するカトリックの神秘主義があらわれているんじゃないかと思うんですね。 先ほど、「プロテスタントによる道徳と勤勉の時代」に「反旗を翻した」と言いましたよね。キリスト教の、とは言わなかった。なぜなら、カトリックの神秘主義とプロテスタントの抑圧というのは、かなり距離があるからです。その証拠に、ワイルドにしてもその理解者ロバート・ロスにしても、ビアズリーやワイルドが尊敬してたJ-K・ユイスマンスにしても、みんなカトリックに改宗しているんですよ。プロテスタンティズムの抑圧、言い換えれば偽善に反抗した末のカトリックへの逃避。だから、この小説は怪奇趣味の姿を借りて、カトリックの神秘主義を描いたんじゃないかと思うんですね。そのあたりを、以下に考察してみました。 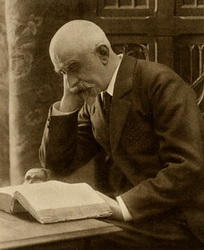 Joris-Karl Huysmans その唯美主義は作者ワイルドの実人生を投影するのにうってつけですから、だれでもここにワイルド自身の影を見るわけです。それは間違ってはいない。ワイルドは同性愛による猥褻罪で投獄され破産しましたよね。恋人であったアルフレッド・ダグラスに破滅させられたようなものです。だから、この小説ではワイルドの芸術至上主義がドリアン・グレイの美の追求に置き換えられて、その末路もまた現実のワイルドと同じ、破滅であると―。 また、皮肉と機知に富んだ警句家ヘンリー卿をワイルド自身の投影であろうと考える人もいます。これは当時から、世間がワイルドに対して抱いていたimageとぴったり重なりますからね。 しかし、唯美主義の追求だけでは小説が保てない。保てないというより、ワイルドはそれで終わらせはしなかったんです。その証拠に、はじめのほうではこの肖像画がドリアンの「良心の目に見える象徴」であると書かれていたのに、終わりの方になると、この肖像画が「ドリアンの人生を傷つけた」とされている。 翻って、ワイルドの唯美主義がその破滅の一因だとしたら、ワイルド自身のその先は? 頽廃の雰囲気に覆われていることで見えづらくなっているかもしれませんが、ここで展開されているのはあくまで偽りの享楽主義であって、「さかしま」のデ・ゼッサントが最後は身体を壊してしまうように、人生が芸術を模倣することはできないという事実が突き付けられているのです。ドリアンはじつは恋人が自殺した時点で、肖像画(芸術)が自分の人生を模倣していると感じています。しかし時すでに遅し、後戻りすることなく堕落の道をまっしぐら。それでも倫理観があるからこそ、肖像画は醜くなっていったわけです。まったく気づかないでいたものが突然眼前に現れるのではない、うすうす気が付いていながら、目を背けていたものが否定しようもない形で現れるのが、いちばん恐怖なんです。だから、肖像画は徐々に醜くなっていった・・・。 ワイルドはもともと幼少期にカトリックの洗礼を施されていましたが、教会には登録されていなかったためにプロテスタントとして生きてきました、彼がカトリックに改宗したのは死の前日です。しかし、プロテスタントへの反抗からことさらに反道徳的な享楽主義者として世間の前で自らを演出していたワイルドは、その生涯のかなりの期間、カトリシズムの影響下にあったものと思われます。 この小説中でも、プロテスタントの主教bishopに対しては、「ものを考えない」と批判的で、カトリックの司祭priestに対しては、ドリアンが好意的に眺めている様が描写されています。はっきりと、「ローマカトリックの儀式にひどく惹かれていた」とも書かれている。結構、ワイルドの宗教感情がそこここにちりばめられているんですよ。教会という制度には否定的でありながら、儀式に対する嗜好とか愛着を示しているのです。そこに、ワイルドのキリスト教理解があるのです。 そうした儀式への傾倒に、ワイルドの唯美主義を見ることもできるのではないでしょうか。そこに、芸術至上主義と宗教感情が共存・両立しうる領域があると感じていたのではないか・・・そのように想像することも可能でしょう。そう考えると、この小説は唯美主義の悲劇を描いたのではなく、唯美主義の破綻を描いたものということになります。 最後の、ドリアンが肖像画をナイフで破ると、ドリアン自身が醜く変貌して死ぬという結末・・・これはふたとおりの解釈が可能で、ひとつには唯美主義の敗北。つまり唯美主義の否定。もうひとつは、唯美主義の不徹底、つまり道半ばで挫折して後戻りしようとするドリアンの敗北。 これは、ワイルドのキリスト教徒(カトリック者)としての意識を鑑みれば、やはり終盤におけるドリアンの良心の呵責を真実とみるべきではないでしょうか。ただし、肖像画の破壊は、神に自らの罪を告白できないドリアンの隠蔽行為なんですよ。肖像画は罪の証拠ですから、証拠隠滅。ところがドリアンは死んだ。つまり、「神は見ていた」ということなんです。 「カンターヴィルの幽霊」あたりとくらべてみてご覧なさい。そこには風刺や皮肉が効かせてありますよね。ところが、「ドリアン・グレイの画像」は、どう読んでも風刺したり皮肉ったりしている様子がない。幻想味なんて言ってしまいましたけどね、この小説の後半で描かれているのは怪奇幻想に仮託した「現実」「真実」なんですよ。私にはこれが、プロテスタンティズムの偽善に対するカトリシズムの神秘主義がもたらしたものではないかと思えるのです。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「ドリアン・グレイの画像」 オスカー・ワイルド 西村孝次訳 岩波文庫 Diskussion Parsifal:ドリアン・グレイは問題の肖像画を、自分以外の人間の目にふれないように保管するよね。つまりだれもドリアンの実像に視線を向けることができない状態であるということだ。たとえば、自殺するシビル・ヴェインがドリアンのことを「麗わしの王子」"Prince Charming"と呼んでいるけど、これはオーノア夫人の「青い鳥」に登場するシャルマン王Roi Charmingからとられた名前だろう。つまり、シビルはドリアンに理想の男性像、自分が勝手に作り出した虚像を見ているわけだ。偶像崇拝だね。 Hoffmann:ドリアンの方も、シビルに自分が思い描く恋人像を投影しているんだよ。だから、舞台上のポーシア、コーディリア、オフェリア、ジュリエットであるシビルにしか興味がなくて、生身のシビルには失望してしまって、捨ててしまう。 Kundry:それが契機で肖像画が邪悪な表情に変化していくのですね。あくまで、自己理解、他者理解ということが、視線の次元から逃れられないんです。だから同性愛であれ、異性愛であれ、その恋愛感情はまさに「感情」であって、対象を理解するところまでは及ばないんですね。 Parsifal:視線にこだわっていないのはヘンリー卿だけだね。ヘンリー卿の機知や逆説、皮肉はポーズだから。結局良識派。だからドリアンの本質は見抜けない。 Hoffmann:やっぱり、これはドッペルゲンガー要素が強いんだな。ドリアンは、だれも視線を向けることがない、自分だけが知っている自己像との決別を図るんだから。その自己像は他者の視線にさらされていないから、社会的に孤立しているんだよ。自己像を確立できないということは、つまりidentityが引き裂かれているということだ。 Parsifal:社会にも、個人の内面においても、身の置き所がないわけか。 Hoffmann:ひとつ、付け加えておこう。この小説の中でドリアンが読んで「影響を脱することができなかった」としている本について、ワイルドはある書簡のなかで「私がまだ描いたことがない本の一つです。しかし、部分的に着想を得たのは・・・ユイスマンスの『さかしま』です」と言っている。もっとも別の書簡ではその本は「存在しません」とあるので、先ほどは話さなかったんだけど。 Parsifal:唯美主義という点では、たしかにワイルドのユイスマンスへの傾倒があると思うね。ユイスマンスはHoffmann君が言っていたように、カトリックに改宗しているんだけど、そのタイミングが・・・「ドリアン・グレイの画像」と同年1891年に「彼方」を書いて発表して、その翌年、1892年のことなんだよ。この事実がオスカー・ワイルドに影響を及ぼさなかったとは考えにくいくらいだ。 Klingsol:三島由紀夫に、この「ドリアン・グレイの画像」を倒立させたような小説がある。 「孔雀」といって、遊園地で27羽の孔雀が殺されるんだけど、近所に住む資産家が2時間余りも孔雀を見ていて飽きないほどの関心を示していたことがわかる。この資産家、富岡は45歳ほど。その客間の壁には16、7歳の「ちょっと類のないほどの美少年」の写真が飾ってある。それは富岡の17歳の時の写真だった・・・。やがて孔雀殺しは野犬の仕業とわかるんだけど、富岡はそんなことは決してないと言い張る。すると、遊園地に「もう一度やる」という怪電話がかかってきて、その晩、富岡と刑事は孔雀小屋の陰に身をひそませる。そこに、犬を連れてやってきたのは、富岡家の壁に見た美少年だった・・・。 つまり、三島にとっては、美とは絶対至上のものだから、観念の中にしか存在しえない、というわけだな。「金閣寺」と同じで、現実の美は滅びなければならない、そうしてはじめて絶対の美となる・・・だから現実の富岡はすっかり老け込んでいるが、写真の美少年はいつまでも若さを失わずに美しくある。しかしその若さと美は魂が抜け落ちるように、富岡からは失われている。そこで美への殉教精神が、額縁の中から抜け出して、孔雀の美が永遠のものになるように、死を与えようとしていたわけだ。 |