068 「オリンピア」 ”Olympia” (1938年 独) レニ・リーフェンシュタール 「オリンピア」"Olympia"(1938年 独)は1936年ベルリンオリンピックの記録映画で、「民族の祭典」"Fest der Volker-Olympia Teii I"と「美の祭典」"Fest der Schoenheit-Olympia Teil II"の二部からなる作品です。監督はレニ・リーフェンシュタール。 「民族の祭典」は開会式から男子マラソンまでの21種目、9日間の記録、ギリシャ古代遺跡に始まり、ヒトラーご満悦の開会式も。100mを走者と同じ速度で併走する移動撮影装置で撮られた映像など、なかなか見せ場も多い。「美の祭典」はオリンピック村のスケッチから第一部で取り上げた以外の競技の模様を、切り取っている。   "Fest der Volker-Olympia Teii I" 厳密な意味でのドキュメンタリー作品でないことはもうよく知られていますよね。記録フィルムに実際の競技映像ではない再現フィルムを加えているし、そのなかには競技後に選手を集めて撮りなおした映像、効果音、練習中の映像なども含まれています。画面の流れを重視してフィルムの裏焼きなども行われているし、選手やヒトラーの肉声以外のほとんどがアフレコだとも言われています。 こうした演出・創作行為に対する批判は当時からあったんですが、フィルム感度やマイクの集音能力の問題もあって、やむを得ないとも言えるし、積極的に作り込んだのだと思えばそれはそれでひとつの考え方だと思います。東京オリンピックの時にも、市川崑監督の「東京オリンピック」についても、やはり創作的な演出が施されているという指摘・非難がありましたね。それは記録を残すか、作品を創るかの問題でしょう。    "Fest der Volker-Olympia Teii I" むしろ私が気になるのは、開会式での、あるいは競技を見てご満悦の様子であるところが映るヒトラーの姿を観て、これをもってこの映画が政治的プロパガンダだ、と大騒ぎする人がいることです。リーフェンシュタールのカメラにしても、その狂熱的な古典美の肉体礼賛こそが、病的な健康主義(おもしろい形容だ)というナチズムの基層であるなどと指摘するのはあまりに幼稚で短絡的。だってそうでしょう、これがナチス賛美のプロパガンダ映画だというのは、第二次世界大戦後だから言えることなんですよ。 急いでことわっておきますけどね、私はヒトラーもナチズムもレニ・リーフェンシュタールも擁護するつもりはなくて、もっと根本的な問題だと思っているんですよ。ヒトラーのプロバガンダだなんて、そんなちっぽけで些末なハナシじゃないのです。   "Fest der Schoenheit-Olympia Teil II" 昔、私が子供の頃、「アストロ球団」という漫画がありましてね。そのなかでビクトリー球団を率いる峠球四郎が、「なんでも原点にかえること」と言って、スポーツだって元をたどれば殺し合いだというような主張をして、アストロ球団を相手に殺人野球を繰り広げるんですよ。といっても、途中からは普通の野球になるんですが・・・しかし、「原点にかえる」という発想、あるいはことばだったら「語源に遡る」という考え方が、物事の本質を知るのになかなか有効な方法であることは確かです。 映画によく描かれたローマの円形闘技場、すなわちコロシアムを思い出して下さい。ローマ皇帝ときたらどいつもこいつも血に飢えた残虐性もむき出しに、キリスト教徒を迫害死に追いやる。映画の主人公たちは生き延びるがために、どこのどいつやら分からない剣闘士や、場合によっては仲間たちとの殺し合いを演じさせられる。その一方では女子どもたちは腹を空かせた猛獣に八つ裂きにされるという愁嘆場。それを観ているのは善きローマ市民。それをまた観ているのが映画の観客たる現代人。そう、いまTVの前に陣取っている現代人こそ、かつてのローマ自由市民の視線を受け継いでいるのです。  "Fest der Volker-Olympia Teii I" なにが面白くて観ているのかというと、鍛え上げられた剣闘士の肉体がもたらすカタストロフィー。つまり、スポーツを観戦している感覚には、こうした阿鼻叫喚や死への予感がつきまとっているのではないか。スポーツというものは必ず死と暴力を内に秘めている。それを背後に隠したまま、「観る」祝祭としたのが19世紀末、1896年の近代オリンピック第1回大会です。 その背景には、「神は死んだ」とニーチェが言い、人々の宗教的なよりどころが失われたという状況があります。それではと、神に代わって宗教的儀礼の役割を担うことになったのが、人々を集団的陶酔に誘い込むスポーツでした。 折も折、産業革命以降中産階級は苦役労働をすることがなくなった。肉体を使う機会がぐんと減った。余暇も増えた。食うのにも困らない。おまけに宗教改革で個人主義が共同体宗教を脇に追いやった。そこにスポーツ。「がんばっている」という快感、満足感がもたらされる。宗教なき時代の疑似宗教として、共同体に狂信的につながろうとする、自ら陶酔したいという願望をかなえてくれる。スポーツにはそれがある。  "Fest der Schoenheit-Olympia Teil II" その危険なスペクタクル性をあっさり見抜いていたのがヒトラーです。もともと国家にとって、スポーツ振興はnationalism台頭の動きに与するものとしてまことに都合がいい。植民地主義には頑健な兵士が必要なのは言うまでもなく、ナチス・ドイツに至っては、「民族」の概念を喧伝するにも使える。スポーツはキリスト教を超えてギリシア・ローマへの回帰であり、「国家」「民族」という強固な共同体のパワーになり得る。ヒトラーはこれをアーリア人男女の肉体崇拝という形で喧伝し、ワンダーフォーゲル運動からボーイスカウトへの流れをヒトラー青少年隊(ユーゲント)の運動にすり替えていった。さあ、あとはオリンピックを招致するだけだ―。スポーツは国家宗教に祭り上げるのにうってつけでした。 さらには、ダーウィンの進化論がこのヒトラーの企みに手を貸すこととなったのです。つまり、1859年に発表された「種の起源」によって、弱者は強者に淘汰されてもしかたがない、いや、むしろ淘汰されるべきものだという、この上なくわかりやすいメッセージが社会全体に浸透していました。筋骨隆々たる剣闘士こそが尊い、優秀の名に値する。淘汰されるべきものは淘汰されてしまえ。 無意識かも知れませんが、それであわてて海水浴だの登山だのがその頃から流行しはじめたのです。ところが共同体は解体されてしまっている。だから、大衆はことさらに厳粛に神聖化された「見るスポーツ」に流れていったわけです。 その延長線上にあるオリンピックが、なぜ「民族の祭典」であり、「美の祭典」であるのか、もうおわかりですよね。   "Fest der Schoenheit-Olympia Teil II" 「祭典」である理由は単純です。産業化による日常とはかけ離れた儀礼性、聖性をもたせるため。厳粛化すればするほど大衆扇動には効果的だから。つまりケとハレの「褻(ケ)」。 そして、そこに自分も属することができる「国家」とか「民族」という共同体が用意されている。その幻影に「狂信」して「熱狂」する。そうしたことによってもたらされるのが共同体復活。「ファン」とは「熱狂者(ファナティック)」の短縮形。つまりは宗教用語。ファンの対象はじつは暴力的な剣闘士であって、ファンの熱狂はまさしく狂信。剣闘士は「英雄」扱い。「ファン」はその英雄と同じ共同体に属していることで自己陶酔して、幸せでいることができる。 ゴルフにマラソン、サッカーに野球・・・TVの前で倒錯的な熱狂を繰り広げ、なんでもかんでも「自己責任」で片付けて、その理屈なら本来淘汰されるべきはずである、己の不器用な肉体の存在を忘れている愚かしさ。国家のnationalismも含めて、似非共同体の疑似宗教は、本来そこから最も遠いところにいるはずの「ファン」の「性」と「暴力」への渇望によって、かろうじて保たれているという矛盾。「ファン」は他人(スポーツをしている本人)の感覚を、「観る」ことで共有しているかのように酔える倒錯趣味という意味で、ほとんど神がかり的な巫女と同じなのです。 さて、このあたりではっきりさせておきましょう。私が言っておきたいことは次の2点です― 1 この記録映画は、ナチスのプロバガンダに利用されました。 2 しかし、この記録映画は、ナチスのプロバガンダ映画として制作されたものではありません。 にもかかわらず、「ああ、いいように利用されただけだったんだね」ではすまされない胡散臭さを漂わせるのは、スポーツとか国家対抗の競技というものが自ずから帯びているイデオロギーに理由があるということです。 もちろん、これはレニ・リーフェンシュタールについても検討したうえでの結論なんですが、そのあたりのことは今回は省略して、以下に、ナチス、ヒトラーのプロバガンダ、国民の洗脳手段のひとつについて、お話ししておきます。 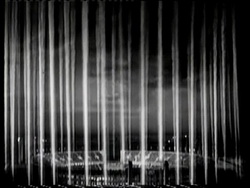 "Fest der Schoenheit-Olympia Teil II" ヒトラーは「記念式典」というものの効果をよく理解していました。ヒトラーに関しては、政権掌握の記念日である1933年1月30日にはじまる「記念式典」は、以後毎年同じ日に国民議会におけるヒトラーの演説がラジオで放送され、彼が委ねられた権力によってなにを成し遂げたかが「国家」に伝達されるという形で「繰り返さ」れました。2月24日は1920年の25項目の綱領の布告の記念日、3月16日はワイマール共和国から引き継がれた第一次世界大戦の犠牲者のための追悼式典、3月最後の日曜日は14歳になる者が総統への忠誠の誓いを立てる通過儀礼をもってヒトラー・ユーゲントに加入する式典、これはキリスト教における信仰告白式を模倣したものです。4月20日は総統の誕生日、5月1日のメーデーはやがてドイツの民族共同体Volksgemeinschaftの祭典となり、6月21日はSS(親衛隊)とヒトラー・ユーゲントによる夏至祭・・・ああ、もうきりがありません。 こうした式典が、国民に対して強烈にカルト的なパワーを吹き込むという点で頂点に達したのは1935年。16人の「血の証人」(失敗に終わったビアホール一揆で殺害された16人の党員)の遺骸が掘り出され、厳粛な行進で、新設された英霊寺院に運び込まれた時でしょう。16人の犠牲者の名が読み上げられ、16発の大砲が鳴り響き、ヒトラーが追悼の花輪を捧げた・・・。これは見事なまでに、宗教的な語彙を含んだキリスト受難劇の再現とも言えるものでした。つまり歴史上の事件を神格化して人々の記憶に植え付けることによって、その事件は絶対不変の実体へと変貌を遂げたわけです。 だってそうでしょう、政治的失策による敗北が、無意味でも無駄でもなかった、むしろ貴い犠牲であったという再解釈が国民の記憶に植え付けられるのです。しかも権力の掌握が、単なる政治的成功ではなく、「帝国」を実現するための「神聖な」事件であったということにもなる。なぜそれほどまでに社会に記憶されたかというと、多分に宗教的儀礼の形式でそれを行ったからなのです。つまり、演じられたカルト。過去形ではなくて抽象的な現在形で語り、演じられることによって、神話的事件を思い出させ、現実の美として再現するからです。 じつは初期キリスト教だって異教の儀式を真似ているんですが、ナチスはキリスト教の要素をそのままに、あるいは新たな要素に差し替えるなどして、同等以上に巧みに取り入れています。つまり「伝統」のないところに「伝統」を作りあげてしまう手腕は見事なもの。こうした儀礼行動はその場だけのものとはならず、儀礼以外の行動や精神活動にも浸透するところに特徴があります。反復することによって、過去からの連続性を暗示する。ナチスに過去なんかないのに、連続性を主張する。ましてやオリンピックといえば古代ギリシアに端を発する祭典です。ヒトラーとってもまことに利用価値のある記念式典であり、宗教儀礼であったのです。 ※ 私が今回観たのはPathfinder Home Entertainmentから出ている2枚組DVD、"OLYMPIA The Complete Original Version"です。 (Parsifal) 引用文献・参考文献 「社会はいかに記憶するか 個人と社会の関係」 ポール・コナトン 芦刈美紀子訳 新曜社 |