117 「沖縄怪談 逆吊り幽霊/支那怪談 死棺破り」 (1962年 大蔵映画) 小林悟 映画「沖縄怪談 逆吊り幽霊/支那怪談 死棺破り」は1962年の大蔵映画、監督は小林悟。 大蔵貢率いる大蔵映画が1962年に台湾との合作で製作した猟奇怪談もの。当時のポスターを見ると、あたかも2本の別の映画のように見えるのですが、「支那怪談 死棺破り」(東方影業/邵羅輝監督)は劇中劇。おまけに「太陽の怪物」"Hideous Sun Demon"(1959年 米)を輸入して、「米国怪談 太陽の怪物」と邦題を付けて併映。「沖縄怪談/支那怪談/米国怪談」とタイトルを並べたもんですから、たいがいのひとは3本立て興行と思いこんだ。じっさいは先に述べたとおり「支那」は「沖縄」のなかで語られるエピソードですから、「太陽の怪物」との2本立て。もちろん、大蔵貢が仕掛けた宣伝なんですよ。   美人の社長令嬢と結婚して逆玉にのった男が原因不明の病気になって、妻が運転手と浮気している妄想にかられます。ある日枕元に妻を呼んで、中国に伝わる話をする・・・これが「支那怪談」。堅い操をたてた貞淑な妻が夫の死後、若い男が現われると、彼のために死んだ夫の脳ミソまで取り出そうとして・・・という話。この話を聞いた妻は、ほかの男が自分に言い寄らないように、自らその美しい顔を傷つけます。その後夫の病気は回復しますが、妻の顔は傷が化膿して、ふた目と見られぬ有様となってしまい、夫は妻に愛想をつかし、愛人を作って毎日午前様。しかしこの夫、もともと婿養子なので財産はすべて妻名義、そこで財産を奪うためにゴロツキを雇って妻を殺害させます。殺された妻は怨霊となって・・・というstory。 まあくだらないといえばくだらないstoryです。死にそうな病床にあって、おれが死んでもほかの男とイチャつくなってダダこねる男もどうかと思うし、そんな夫を安心させようと顔面に傷をつける妻というのも、考えたらこれは似合いのバカップル? 「支那怪談」を別映画と見せかけたのはともかくとしても、さらに劇中劇の思いっきり安造りなセットに目をつぶっても、これは脚本の水増しとしか見えません。  そんなことよりも、私が興味を引かれたのは表題どおりの「逆吊り幽霊」。ドリフのコントでも頭を下にして上から登場する幽霊(人形)というのはお馴染みでしたね(古いな)。この、逆さまの姿というのは、ちゃんと伝統に則っているんですよ。この映画のなかでは、妻の幽霊が、ひどい夫に足に釘を打たれてこんな姿で・・・と和尚に訴えるんですが、ルーツは鶴屋南北の「東海道四谷怪談」、蛇山庵室の場において、お岩の亡霊が門口の提灯から現れるところ。文政8年(1825年)の初演時ではなく、天保2年(1831年)、三代目菊五郎が5回目の上演にあたって採用したとされる「提灯抜け」がそれ。もっともこうした趣向はこれ以前からあったとも言われており、ここに幽霊が「さかさま」で登場する、あるいは描かれるのはなぜか、といった問題が浮きあがってくるわけです。そのあたりを考察したのが、服部幸雄の「さかさまの幽霊」(ちくま学芸文庫)。  書影 これによると、提灯という球形で内部が空洞になっているものには、霊魂が宿っているという民族の心意が働いていたのであろうとされています。玉・珠は本来魂(たま)と同根の語であると。それでは、こうした演出では幽霊が提灯から出るという所与の条件のために、やむを得ず逆さになって出現したのか・・・。これは日常ならざる怨霊の舞台的形象化にあたって、怨霊事に劇としての飛躍を求めた、そこに殺された女の一念を異常な形で顕現させるための趣向であったとしています。「恐ろしい形相」「一念の凝った性根」「怨霊にふさわしいことばや身振り」。その性根や男を超える強靱な力、それが「さかさま」の力の発現であるというわけです。そのための手段が、身軽さという役者の天性と修業を活用しての軽業事。じっさいに当時の芝居では、「東海道四谷怪談」に限らず、幽霊が逆さまの形で出現することはめずらしくなかったようで、観客の側でも逆さまの幽霊に関する知識があったらしい。単純に逆さまということが尋常でないものをあらわしていたとも考えられますが、逆さまなるものに霊異の力を認めることが日本の伝統的な発想であるとする意見もあります。   「東海道四谷怪談」からお岩の亡霊、坂東彦三郎と民谷伊右衛門、片岡仁左衛門。いずれも中村座にて,文久元年7月11日(1861年8月16日)に上演された際のもの。三代歌川豊国(国貞)による。 なお、エリアーデによれば、似たような考え方は、北アジアにもありました。他界はこの世が逆さ映しになったものであるという発想です。この世の昼は彼の国の夜、冥界では川が水源に向かって流れている・・・。これ、中世ヨーロッパ人が考えたアンティポデスと共通する世界です。すなわち地球の裏側、アンティポデスではどこからどこまで自分たちとは正反対の生き物が棲息していると考えられていました。おもしろいのは、地球の裏側に逆立ちしてぶら下がっている連中はどうして下に落ちないのだろう、という疑問に対して、「彼らもまた私たちが落ちないことに驚いているであろう」と言った、15世紀の博物学者ハルトマン・シューデルですね(笑) ちょいと話が脱線しますが、現代人だって、こうした中世人を笑えませんよ。20世紀に至っても、おかしな学説(?)を唱える人はたくさんいて、たとえばアンティボデスで連想するのは地球空洞説。これを応用して、我々が立っている地表は、じつは地球の内部だと言いだしたのが、アメリカの学者、C・R・T・コーレッシュ博士。これによると、宇宙はひとつの球体の中に閉じ込められており、その直径はわずか12,750km。狭いなー。地球の表面も凹状。つまり、人間も大陸も海も球体の内壁にへばりついており、重力の正体は遠心力であるというわけです。ニュートンもびっくり。なんだかラリイ・ニーヴンの「リングワールド」みたいですね。もっとも、このような発想は、それこそプトレマイオス以来の球殻宇宙観に神秘学を融合させて、ついでに母胎回帰願望を投影したものと思えないこともない。プラネタリウムなんて、その形象化と言えるかも知れませんよね。 さらに荒唐無稽なのは、太陽系の惑星は数珠つなぎになっていて、空に見えるのは空気の屈折のためであるとする主張。これによると、北極点に到達すると別な惑星に歩いて行けるということです。そのほか、たしかアメリカには「宇宙は野菜に満ち満ちている」と唱えている宗教団体も。意味が分かりません(笑)そんなのにくらべたら、ハルトマン・シューデルなんか「相対化」ができているだけ、余程まともです。 地球空洞説といえば、これがはじめに提唱されたのは19世紀初頭、フランスとアメリカ、ほぼ同時です。このとき、アメリカで言いだしたのは陸軍大尉なんですが、その意図は領土拡張。合衆国議会に自説の支持を求めるも相手にされず。ところが、20世紀になってアメリカの気象衛星が撮影した、北極に真っ黒な穴が空いている写真で地球空洞説がまたまた話題になりました。その写真をご覧下さい。単にカメラのアングルの関係で写っていないだけだとする説もありますが、よく注意して見て下さいよ。地球一回り、全部日があたっている(昼間である)・・・ンなわけないでしょ。つまりこれは時間をおいて撮影した複数枚の写真を合成したもの。それでも北極周辺が真っ暗だということは、つまり日が昇らない極夜の季節の写真なんですよ。うっかり騙されちゃった人が、後に「穴があったら入りたい」と言ったかどうかは分かりません。 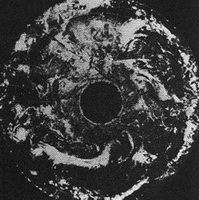 例によって話が大きく逸れてしまいました(笑)私、ひさしぶりにこの映画を観るにあたって、わざわざ泡盛なんぞ用意してモニタの前に座ってしまいましたが、これは往年の東京12チャンネル(これも古いな)あたりで放送しているのを、寝そべってながめている方がふさわしかったような気がしますね(笑) (Hoffmann) 参考文献 「さかさまの幽霊」 服部幸雄 ちくま学芸文庫 |