161 「インフェルノ」 "Inferno" (1980年 伊・米) ダリオ・アルジェント 世界中でセンセーショナルな成功を収めた「サスペリア」によってオカルト・ホラーという新機軸に踏み込んだダリオ・アルジェントに期待された次の作品が「インフェルノ」です。「サスペリア」に続いて魔女が重要なモティーフとされたこの作品、錬金術師に焦点を当てて、ゴシックとアール・デコが融合したような建築物とその由来で、前作との関連を示唆しています。 あらすじは― 舞台はニューヨーク。ローズは近所の骨董屋で「三母神」"The Three Mothers"という本を見つける。そこに綴られていた建物に関する記述から、彼女がいま暮らしているアパートのことであることがわかる。 「三母神」の著者はバレリ。幾世紀前の建築家らしいその男は、3人の魔女のために家を建てたという。場所はフライブルク、ローマ、そしてニューヨーク。ローズが住んでいるのはその魔女「暗黒の母(マーテル・テネブラルム)」のために建てられた館ではないのか。彼女は弟マークにそのことを知らせる手紙を投函した後、好奇心からアパートの地下室を調べはじめる。地下室には水がたまっており、そこには死体が・・・。 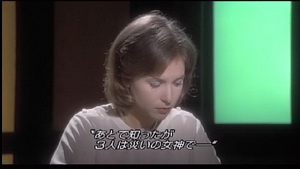  「サスペリア」の成功を受けてほとんど間を置かずに制作された、本来ならこれこそが「サスペリアPART2」と呼ばれるべき作品です。舞台をニューヨークに移したのはアルジェントとしては初のアメリカ資本による作品だからかもしれません。じっさいの撮影はほとんどローマのスタジオで行われていますが、部分的にニューヨーク・ロケも行われているとのこと。音楽はゴブリンではなくてキース・エマーソン。 storyはシンプルだった「サスペリア」とくらべると、ずっと複雑になっています。当初ヒロインかと思われた主人公マークの友人が殺されて、それではこちらがと思った姉ローズも殺されてしまう。このあたり、ちょっとヒッチコック風ですね。 冒頭で謎の核心である、三人の母=魔女が説明されてしまい、魔女の館の地下室に肖像画がある、その館の周辺は甘い匂いがする、靴底を探れ・・・この3つのキーワードを解いてゆく過程が、storyのすべてといっていいものです。その意味では、観客には早い時期にすべてが明かされてしまっており、知らずに姉ローズを探し続ける主人公マークは魅力に乏しく、共感もできない存在。だから一般的には「失敗作」なんて言われてしまう。   ただし「仕掛け」はいろいろ細々とあって、魔女の棲むニューヨークの館と、ローマの古文書図書館の壁にはそれぞれのシンボルであるドラゴンと蜥蜴が彫り込まれており、重要な箇所でチラ見せしています。地下室には水がたまっており、これを対応するように、真相が明かされる直前に失神した主人公は海辺の映像を夢見る(幻視する?)。  主人公を秘密の地下室へと導くのは、蟻。これはダリオ・アルジェント自身が言っているように、この物語が「ヘンゼルとグレーテル」を下敷きにしているから、つまり「魔女の館」はお菓子の家だから。周辺は甘い匂いがするというのもそういうことなんですね。 冒頭の地下室の特殊効果はアルジェントにとっても大先輩であるマリオ・バーヴァが担当。ラストの鏡から死神が出てくるシーンも同様、一部セットのデザインや演出も含めて、疲労でダウンしたアルジェントの代わりを務めています。  結果的に前作ほどのヒットにはなりませんでしたが、個人的にはそれなりの佳作より以上の出来だと思います。唐突でつじつまの合わない、見せたい場面を見せることが優先・・・というのは、骨董屋の店主がホットドッグ屋に殺害されるシーンや(なにが起きたんだ?)、図書館の地下に火にかけられた鍋が並んでいるところ(なんでこんなところにこんな部屋が?)、それに布を切り裂いて現れる死体など(この布はなに? どこから?)。たとえば最後の死体発見の様子は、観客は既に殺されるところを観ているから、主人公が普通に死体を発見しても面白くないのでこうしたのでしょう。あくまでも観客を驚かせる画面造りが優先されているんですよ。しかしダーク・ファンタジーの異空間が現出したものと思えば、そんな脈絡のなさも、強引かつご都合主義も、これがアルジェントの「映像美学」だろうと許せてしまうところがあります。   主人公の姉ローズ役のアイリーン・ミラクルは学生時代にシンクロナイズド・スイミングの選手だったんだとか。ああ、だから起用されたんですね。車椅子の老人はロシアの伝説的オペラ歌手シャリアピンの息子、フョードル・シャリアピン・ジュニア。「薔薇の名前」にもご出演でしたね。アパートの管理人が前作に続いての出演となるアリダ・ヴァリ。脚本執筆に当たって貢献したダリア・ニコロディはなぜかクレジットから名前を外されて、アパートの住人という脇役。どうもこのあたりからアルジェントとの仲が険悪になったらしい。それでも上記出演陣は上出来です。問題は主演のリー・マクロスキーで、このアメリカで売り出し中だったTV俳優は、スポンサーである20世紀フォックスのごり押しだったそうで、ハリウッド・スター気取りのボンクラ俳優。ロクに演技も出来ないのに現場ではわがまま放題で、スタッフや共演者からはソッポを向かれてしまい、これがアルジェントが疲労でダウンした原因であったようです。  ヴェルディの歌劇「ナブッコ」の合唱「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」"Va, pensiero, sull'ali dorate"が効果的に使われています。このユーフラテス河畔でヘブライ人たちが祖国への想いを歌う音楽は、イタリア人にとっては「イタリア統一運動(戦争)」と結びついて、かなり特別な意味を持つ、謂わば「心の国歌」ですからね。 (Parsifal) Diskussion Parsifal:さて、前回に引き続いてHoffmann君と意見交換したいと思います。 Hoffmann:「インフェルノ」は失敗作なんて言われることもあるみたいだけど・・・。 Parsifal:前回引いてた批評には、「インフェルノ」に関して、「内容よりスタイルを優先」、「ストーリーはまったくもって意味をなさず」というのがあったよね。いや、そのとおりなんだけど(笑)それこそがダリオ・アルジェントなんで。 Hoffmann:「サスペリア」よりもstoryが複雑になった分、余計にそう見えてしまうんだろうね。でもねえ、ダークな雰囲気はなかなかのものだと思うよ。Parsifal君が言っているように、主演のマーク役の俳優がダメにしてしまっているんだ。スポンサーのゴリ押しというのはロクな結果にならないという例だね。 Parsifal:アルジェント映画では、主人公(語り手、視線の主)が男性だと、超自然よりも理詰めのミステリ、サスペンスに、主人公が女性だと、超自然の展開になる傾向がある。その点、「インフェルノ」はなかなかユニークで、謎解き役は男性なんだけど、全篇を支配し、すべてを見(下ろし)ているのは、夜空の「月」なんだ。 Hoffmann:そうそう、まさしく問題のホットドッグ屋の骨董商殺害シーンなんかにそれがあらわされているよね。 Parsifal:「ルナ」"luna"は「月」で、「ルナティック」"lunatic"は「狂気」、もちろん、西欧で古くから満月が人を狂気に至らせると考えられていたことに由来することばだ。もっともあのシーンは月蝕のようだけど。 Hoffmann:ギリシア語で「狂気」を意味する"mania"ということばも、サンスクリット語"ma"に由来している。そこから"maniac"(マニアック)、すなわち「狂気の」ということばが生じたわけだ。"lunatic"(ルナティック)はラテン語の"lunaricus"由来だね。これは「月の女神」と「月」の両方を意味する"luna"(ルーナ)の形容詞形だ。だから狂気というのは、月の女神につきものの恍惚状態のことなんだよ。それがもたらすものが「狂気」なんだ。新訳聖書のマタイ福音書で、イエスがてんかん患者を癒やすけど、当時てんかんは脳内の水分過多によって起こると考えられていたんだ。だから満月にはもっともひどくなると・・・。アリストテレスも乳児の引きつけは満月の時がもっとも激しいと言っている。 Parsifal:月と、月によって乱される心というものの関係は、ヨーロッパ言語によくあらわれているね。 Hoffmann;ドイツ語でも"mondsuechtig"(月の病)は「狂気」を指すし、フランス語でも"avoir des lunes"(月を持つ)といえば、「気がふれる」という意味になる。 Parsifal:それと、月は悪夢を送るともされていたよね。悪夢nightmareはもともと夜の亡霊で、やがてこの霊は魔女と考えられるようになった。フランスならディアーナだな。ローマ時代には、彼女は怒りを招く者に狂気を送るとされていた。ユダヤの言い伝えでは、月光を浴びて眠ることが危険視されている。 Hoffmann:だから狼男も満月で変身するんだよ。 Parsifal:ただ、問題のこのシーンは月蝕みたいなんだよ、満月じゃない。   Hoffmann:月蝕は満月が地球の影に入って、通常の法則にかなった満ち欠けではなくて、突如として暗くなるものだよね。だから古代人にとっては自然の秩序が乱されて、生命が破滅を迎えることだったわけだ。月蝕の「蝕」"eclipse"は「脱落」とか「放棄」を意味するギリシア語"ekleipsis"に由来する語だ。 Parsifal:月から見放されるというわけか。日蝕なら太陽から・・・。 Hoffmann:1995年の日蝕の時にはインドで大騒ぎになっている。月蝕だって、月が死んでしまうことを恐れて、月を助けようと、マサイ族は空中に砂を投げつけたし、北米の先住民族は鍋釜を叩いて、火矢を月に向かって放った者もいたそうだ。似たようなことは、カムチャッカでも、ヒンドゥー教徒の間にも見られている。中国では龍が月を食っているのだと考えて、鏡を叩いて龍を脅かし、食べたものを吐き出させようとした・・・。 Parsifal:とすると、太陽はもちろん、月も守るべきものなんだね。月の死と自らを重ね合わせていたから。 Hoffmann:日蝕も月蝕も、自然の秩序の一時停止だからね、地球にとってよい前兆ではないんだよ。おもしろいことに(と言っては語弊があるが)、日蝕や月蝕の時に、生き物を殺して供犠として天の月に捧げることもあったんだよ。北米先住民は犬を殺したり、赤ん坊を泣かせたりして、これがメキシコになると、こびとや背中に障害を持つ人たちを殺したそうだ。で、月蝕なんて短時間で終わるから、この供犠が効果をもたらしたと思われてしまったんだな。 Parsifal:なるほど、「インフェルノ」の骨董屋も脚に障害がある。ホットドッグ屋は狂気にかられたのか、天界の秩序を取り戻すための儀式を行ったのか・・・。まあ、無理に黒白付ける必要もないかな。すっかり月談義になってしまったので(笑)話を戻そう。 Hoffmann:謎は謎のまま、つじつま合わせを考えなくてもいいよね。でもそもそも映画というものは、storyを重視するだけでは成り立たないよね。段取りの叙述で終わってしまっているドラマがいかに多いことか・・・なんなら多少storyに破綻があってもかまやしないんだよ。だからダリオ・アルジェントはそのフロイト理論などという、ほとんど意味をなさない解説や説明をしない方がいい。説明が少し足りないぐらいでいいんだよ。説明過剰だから、かえってstoryの破綻や行き当たりばったりな展開が目に付いてしまう。 Parsifal:それな(・・・ということばを、一度使ってみたかった・笑)。いっそのこと登場人物に状況説明なんかさせないで、この際つじつま合わせも一切合切放棄してしまえば、唐突に挟まれた、監督が「撮りたかった」シーンも浮いてしまうことなく、それと気付かせずに流れに乗せることができたんじゃないかな、とは思うね。それができていたのが「サスペリア」なんだ。「インフェルノ」はstoryが入り組んでしまった分だけ、説明的になってしまっているんじゃないか。 Hoffmann:でも、やっぱり雰囲気はいいよ。あ、そこはマリオ・バーヴァの功績も相当大きいわけか。 参考文献 「恐怖 ダリオ・アルジェント自伝」 ダリオ・アルジェント 野村雅夫、柴田幹太訳 フィルムアート社 |