180 メシアン 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」 先日Parsifal君がリリアーナ・カヴァーニの映画「フランチェスコ」を取り上げましたね。そこでこちらでは、オペラで描かれたフランチェスコです。中世イタリアの聖者、フランチェスコをテーマとしてオペラにしたのはフランスの作曲家、オリヴィエ・メシアン。台本もメシアンの手になるもので、1975年から1983年にかけて作曲されました。よく知られているとおり、メシアンは敬虔なカトリック信者ですからね。世界初演は、1983年11月28日に小澤征爾の指揮でパリのオペラ座で行われており、この講演の記録はCD化されています。私もそのCDで聴きました。 小澤征爾指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 同合唱団 聖フランチェスコ:ホセ・ファン・ダム(Br) 天使:クリスティアーヌ・エダ=ピエール(Sop) 癩者(ハンセン病患者):ミッシェル・フィリップ(T) 兄弟レオーネ:ケネス・リーゲル(Br) 兄弟マッセオ:ゲオルゲス・ガウティアー(T) 兄弟エリア:ミシェル・フィリップ(T) 兄弟ベルナルド:ジャン・フィリップ・コールティス(Bs)ほか 1983.11.28 live NEC AVENUE A30C-3002~5(4CD) メシアンによる台本はフランチェスコの回心からはじまるもので、ほぼ全篇がひたすら信仰による祈りに費やされています。したがって、キアラとの関係や、父親との争いなどは描かれていません。その意味では、たいへんstaticな劇です。全3幕、8つの場からなるもので、構成は次のとおり― 第一幕 第一景 「十字架」 修道の苦しみを訴える弟子のレオン(レオーネ)に、フランソワ(フランチェスコ)が語る。 第二景 「讃課」 フランソワが癩病患者に出会い、祈る。 第三景 「癩者への接吻」 癩療養所で病気に苦しむ患者にフランソワが語りかける。天使が窓に現れる。フランソワが患者に接吻すると病気が癒えてゆく。 第二幕 第4景 「旅人に身をやつした天使」 ラ・ヴェルナの森に旅人の姿をした天使が現れる。天使が修道院のドアをノックして弟子のマッセ(マッセオ)が扉を開くが、弟子のエリー(エリアス)に質問をするが、彼は答えることを拒み天使を追い出す。天使は再度ドアをノックし、弟子のベルナルドに同じ問いをする。ベルナルドは返答する。 第五景 「音楽を奏でる天使」 天使はフランソワのもとを訪れ、ヴィオールを演奏する。 第六景 「鳥たちへの説教」 フランソワと弟子のマッセは鳥たちに説法する。世界中の鳥たちが喜びを歌いあげる。 第三幕 第七景 「聖痕」 夜のヴェルナの森、岩の洞窟にフランソワひとり。巨大な十字架が現れ、十字架から五条の光線が出て、フランソワの両手両足と右の脇腹に聖痕を残す。 第八景 「死と新生」 死に瀕したフランソワは、すべての人に別れを告げ、太陽の賛美歌「姉妹の体の死」を歌う。弟子たちは詩篇141を歌い、癩者や鳥たちもやって来る。天使が現れ、フランソワを讃える。フランソワは死に、合唱が復活を賛美。 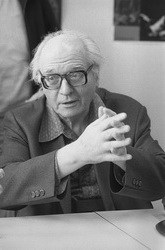 Olivier Messiaen、精確にはOlivier-Eugene-Prosper-Charles Messiaenという長い名前 メシアンが敬虔なカトリック信者であることは知っていましたが、このような台本を書いてまでオペラにしたというのはちょっと意外でした。オラトリオでも単なる合唱曲でも、オーケストラを含む声楽曲ならまだしも、20世紀も後半に至って、前近代的なオペラという形式をとってメシアンが作曲したということが驚き。もちろん、パリ・オペラ座の音楽監督であったロルフ・リーバーマンが1971年にメシアンにオペラを依頼したとき、メシアンも一度はこれを断わっているんですよ。ところがリーバーマンの根回しによって、当時のフランスの大統領ジョルジュ・ポンピドゥー主催のエリゼ宮の晩餐会に招かれ、ここでポンピドゥーから「パリのオペラ座のためにオペラを書いてください」と依頼されたんですね。だからこの作品がオペラになったんだ、といえばそれまでのことなんですけどね・・・。 当初メシアンはキリストの受難または復活を劇化することも考えたらしいのですが、最終的にアッシジの聖フランチェスコの人生を劇化することにした・・・いやあ、劇自体は先に述べたとおり、少なくとも表面的にはさほど劇的ではない、ただし音楽はかなり劇的です。 以前、「ロマン主義時代以降の宗教音楽について」と題して、いろいろ勝手なことを長々と語りましたが、この歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」もまた、その流れの末にあるものと言っていいでしょう。そう考えると、ロマン主義の宗教音楽が概ねレクイエムやミサ曲と題され、オラトリオやカンタータの形式をとっていたのに対して、ここでついに歌劇になったということなのかもしれません。いや、それならワーグナーが「パルジファル」でやっていた? たしかにそのとおり。ワーグナーは「パルジファル」を宗教音楽と明言していたわけでありませんが、「パルジファル」が「アッシジの聖フランチェスコ」の先駆的作品であると見ることはできそうです。しかし、ワーグナーは光に対立する闇の部分も描いて、音楽のみならずstory(リブレット)も劇的なものにしている。対して、メシアンはnegativeな要素は一切合切カットして、あくまで聖者の内面を「劇的に」描いた。 その音楽は、そこここに「トゥーランガリラ交響曲」や「鳥たちの目覚め」「異国の鳥たち」「われ死者の復活を待ち望む」などの響きが聴き取れるもの。これ、R・シュトラウスの「英雄の生涯」は言うに及ばず、たとえばフランスの映画監督ジャン・ローラン(知ってる?)も晩年に過去の作品のシーンを一部コラージュ風に引用していました。人間、功成り名を遂げたり、高齢になって死を意識したりすると、こうしたことがやりたくなるんでしょうか。 私は上記の小澤征爾による世界初演の実況録音のdiscしか聴いていませんが、その後ケント・ナガノ、カンブルラン、メッツマッハーなどのdiscが出ているそうですね。機会があれば入手して聴いてみたいと思っています。 (おまけ) お気に入りのメシアン作品のCDセットを3点― まずはケント・ナガノ盤。2000年にベルリン・フィルと録音した「トゥーランガリラ交響曲」も見事な演奏でしたが、これは2017年から2019年の三作品のlive録音です。 「我らの主イエス・キリストの変容~混声合唱、7つの楽器の独奏と大オーケストラのために」 ピエール=ロラン・エマール(ピアノ) リオネル・コテ(チェロ) ヘンリク・ヴィーゼ(フルート) シュテファン・シリング(クラリネット) クリスティアン・ピルツ(シロリンバ) グイド・マーグランダー(マリンバ) イェルク・ハンナバッハ(ヴィブラフォン) オ・ムンヨン(テノール) マティアス・エットマイアー(バス) バイエルン放送合唱団、ハワード・アーマン(合唱指揮) ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク、2017.6.20-23 live 「ミのための詩~ソプラノとオーケストラのために」 ジェニー・ダヴィエ(ソプラノ) ミュンヘン、ヘルクレスザール、2019.2.11-15 live 「クロノクロミー~大オーケストラのために」 ミュンヘン、ヘルクレスザール、2018.7.3-6 live バイエルン放送交響楽団 ケント・ナガノ(指揮) Br Klassik 900203(3CD)  Kent George Nagano お次はシルヴァン・カンブルラン。これは2008年のメシアンの生誕100年記念リリースだったもの。録音年は1999年から2008年ですから、結構長い時間をかけて準備していた企画だったのかも知れません。「彼方の閃光」「我らの主イエス・キリストの変容」「キリストの昇天」はリリース済みだったようですが、その他は初出。とくに人気の大曲「トゥーランガリラ交響曲」や「峡谷から星たちへ」がカンブルランの指揮で聴くことができるのがうれしい。 「忘れられし捧げもの」(1930) フライブルク、コンツェルトハウス、2002.1.17 「キリストの昇天」(1934) フライブルク、コンツェルトハウス、1999.1.13-15 「ミのための詩」(1948) イヴォンヌ・ナエフ(メゾ・ソプラノ) フライブルク、コンツェルトハウス、2007.12.19, 20 「トゥーランガリラ交響曲」(1948) ロジェ・ミュラロ(ピアノ) ヴァレリー・ハルトマン=クラヴリー(オンド・マルトノ) フライブルク、コンツェルトハウス、2008.2.12, 13 「鳥たちの目覚め」(1953) ロジェ・ミュラロ(ピアノ) バーデン=バーデン、ハンス・ロスバウト・スタジオ、2007.6.27 「異国の鳥たち」(1956) フライブルク、コンツェルトハウス、2008.2.12, 13 「クロノクロミー」(1960) フライブルク、コンツェルトハウス、2005.2.24 「われ死者の復活を待ち望む」(1964) ロジェ・ミュラロ(ピアノ) フライブルク、コンツェルトハウス、2008.5.3 「我らの主イエス・キリストの変容」(1969) グンヒルト・オット(フルート) ヴォルフハルト・ペンツ(クラリネット) フランツ・ラング(シロリンバ) ホルスト・フリーデル(ヴィブラフォン) ヨッヘン・ショラー(マリンバ) ラインハルト・ラツコ(チェロ) フロラン・ボファール(ピアノ) オイローパコールアカデミー、ヨスハルト・ダウス合唱指揮 フライブルク、コンツェルトハウス、2000.12.12-15 「峡谷から星たちへ」(1974) ロジェ・ミュラロ(ピアノ) ティエリー・レンツ(ホルン) ヨッヘン・ショラー(シロリンバ) マルクス・マイアー(カリヨン) バーデン=バーデン、2007.4.25-5.4 「天より来たりし都」(1987) ロジェ・ミュラロ(ピアノ) フライブルク、コンツェルトハウス、2007.4.23-5.4 「ほほえみ」(1989) ミュンヘン、レジデンツ・ヘルクレスザール、2008.1.27 「彼方の閃光」(1991) フライブルク、コンツェルトハウス、2002.2.25, 9.19 シルヴァン・カンブルラン指揮 SWR南西ドイツ放送交響楽団 Hanssler Swr Music 93225(8CD)  Sylvain Cambreling 最後に若杉弘、NHK交響楽団のlive録音です。1996年から98年にかけて3期9公演に亘って行われた若杉弘指揮、NHK交響楽団によるブルックナー・チクルスは「2つの世紀のカトリック」と題されて、各回ブルックナーの交響曲1曲とメシアンの作品を組み合わせたプログラムで構成されており、これはブルックナー交響曲全集に続くメシアン作品のdisc化ということになります。よって録音会場はすべてサントリー・ホール。日本初演作品も少なからず。楽曲解説は当時のプログラムに掲載されたもので、日本語で読める詳細な解説はありがたいですね。 なお、「2つの世紀のカトリック」というテーマはユニークだとは思うし、プログラミングに凝るこの指揮者らしいとも思います。しかしながら、たしかにブルックナーはカトリックなれど、私はその交響曲に宗教的な色彩も、匂いも、雰囲気も、感じとれません。いや、いくつかあるブルックナーの宗教音楽はたしかに交響曲と通じるものがあるんですが、逆に、交響曲が宗教音楽に通じるものだとは思えない。ブルックナーが敬虔なカトリック信仰を持っていたからといって、私はその音楽を理解するのに、ブルックナーのカトリック信仰という事実を知ることが重要だなどとは思っていません(そのように主張する人はよくいるんですが、いったいどのように重要なのか、また、ブルックナーがカトリック信仰であることを知っていると、その音楽に聴き方・聴こえ方がどうなるのか・・・これを説明できる人に出会ったことがありません)。その信仰を疑うわけでありませんが、ブルックナーは聖書もあまり読まなかったひとですからね。いかに若杉弘の好きな私でも、正直なところ、ブルックナーがカトリックであったというだけの「こじつけ」めいた組み合わせではないかと思っています。 メシアン:管弦楽作品集(サントリーホール10周年記念公演 ブルックナー・チクルス1996~98「2つの世紀のカトリック」より) チクルス第1期 「忘れられた捧げもの」(1930)1996.1.29 「教会のステンドグラスと小鳥たち」(1986)1996.2.26日本初演 木村かをり(ピアノ) 「かの高みの都市」(1987)1996.3.31日本初演 木村かをり(ピアノ) チクルス第2期 「われら死者のよみがえりを待ち望む」(1964)1997.1.13 「聖体秘蹟への賛歌」(1932)1997.2.24日本初演 「キリストの昇天」(1932-33)1997.3.18 チクルス第3期 「天国の色彩」(1963)1998.1.27 木村かをり(ピアノ) 「神の顕現の3つの小典礼」(1945)1998.2.28 木村かをり(ピアノ)、原田 節(オンド・マルトノ) 東京混声合唱団(女声)、大谷研二(合唱指揮) 「輝ける墓」(1931)1998.3.13 若杉弘指揮 NHK交響楽団 Altus ALT483(3CD)  若杉弘 (Hoffmann) |