060 「回転木馬」 中村眞一郎 講談社 ※ 「58 『晩夏』」、「59 『われわれ自身のなかのヒトラー』」を先にお読み下さい。 作家の中村眞一郎の回想に、戦時中に知り合った中産階級の娘たちがヒトラーを賛美するのに出会ったが、そのナチスを賛美していた少女たちが、戦後に会ったら、例外なくオランダにおいて逮捕されたユダヤ人の一少女の記録「アンネ・フランクの日記」の愛読者となっていた、というエピソードがあります。これは、もともとナチスを賛美していたのも、「わが闘争」を研究してナチの人種理論に共感したためではなく、家庭における父親あたりの根拠のない総統賛美の言説の受け売りであったのに相違ない、とされており、つまり独立した人格を持っていない、家庭の影に過ぎない幼稚な人類の話です。 では、知識人と呼ばれる人々はどうか―中村眞一郎によれば、多数の知識人は時代の風潮の変化と微妙に歩調を合わせて変節して、いつの時代にも、その時代の要求する思想をうまく主張しているということです。すなわち満州事変から第二次大戦に至る緩慢なファシズム化の時代には、いつの間にか左翼主義者が右翼になり、敗戦となれば一朝にして民主主義者に変貌する、という按配です。これが笑い話でないことは、当時の敗戦前後の1か月ほどの新聞を翻してみればわかることだ、と―。 また、著名な某哲学者は倫理学の著述において、戦前に刊行された上巻では個人の人格を倫理の根本に置き、戦時中に刊行された中巻では国家が倫理の最高目的であると説き、戦後の下巻に至ると、その国家は民主主義でなければならず、そこにおいて個人の人格の伸長と社会とが調和すると説かれている・・・まるで奇術師の軽業ですね。こうして知識人は、つねに時代の先頭に立っているわけです。しかもその個々の著作は、いずれもがなかなか説得力のある名著だと。つまりそれぞれが学者として誠実な研究の成果であり、すなわち個人の人格は統一的ではないということです。こうした知識人は、個人としての人格の一貫性を守るより、日本社会のその時期ごとに要求する思想の解説者としての役割を忠実に果たしている、というわけです。 これは中国や西洋にも見られない、我が国独特の現象であって、たとえばプロレタリア革命を唱える毛沢東と対立したブルジョワ民主主義による蒋介石政権は長年の戦いの末、ついに大陸から撤退して台湾に立てこもりました(余談ながらこうした経緯から見ても、台湾が現在の中国共産党支配に耐えられるわけがないのです)。また、ドイツでナチスの政権が確立すれば、自由主義者や左翼の知識人は大量に亡命して自分の思想を主張し、ナチに転向するという光景は見られませんでした。 敗戦後、復員した知識人のなかから、青年の大部分が前線で苦しんでいるときに、その苦しみを分かたずに反戦だなどと言っていた人間は道徳的に卑劣であるという非難の声が発せられたのですが、この論理からすると、敗戦と同時に日本は民主主義国家となったのですから、民主主義者でない者は非国民である、という筋道の話となり、これも自己便宜的に感じられます。戦場に倒れた多くの戦友のためを思うならば、敗戦後も軍国主義を守らねば申し訳ないという方が、まだしも道徳的には潔癖なのではないか。 さらにおかしいと思われるのが、戦没者は平和のために命を捧げたという戦後に流行した理由付けです。これは真っ赤な嘘であるはず。戦争遂行時の支配的な思想は「天皇陛下のために」というものです。しかし、これを認めると、厖大な戦死者が「犬死に」であったという論理的帰結が見えてくるので、日本語独特の曖昧語の連発と暗黙の了解で、事態の判断を停止したままにしているのです。次の時代の流行思想によって前代の自分の行動を弁護して、一貫性を擬似的に誇示しようという本能かもしれませんが、いくらなんでも、これは苦しいですね。 おまけに、戦時中の戦争責任者は死刑となりましたが、その処罰を逃れた同じ陣営の者たちが、戦後の政界に復帰して国政をにない、戦時中は「鬼畜米英」を唱えていたその口で、今度は「日米安保条約」推進を叫ぶようになりました。 もしかしたら、我が国の哲学者や知識人と呼ばれるひとたちの場合、つねに周囲と同じことを考えて、同じ行動をとっていなければ不安であるという、日本独特の「村構造」から発する変節なのかもしれません。 じっさい、思い起こせば戦国時代の武田氏の官僚群が織田政権に吸収され、織田政権が亡びると、後を継いだ豊臣政権下に多くの織田氏の武将が従い、次の徳川家康になると、豊臣方で戦った大名たちは粛清されたものの、行政官の大部分は新政府に採用されています。もちろん、19世紀後半に徳川幕府が崩壊して、薩長を中心とする新政府が東京に誕生したときも、行政官の9割方は旧幕府官僚であったわけです。しかし、彼らは変節漢として非難されることはなく、自分の能力を国家に役立てたものとして尊敬を集めている。転向者も、後ろめたさを感じていないのです。ここに、我が国特有の「村落的社会」という社会集団の特性が見られるのです。 転向者が非難されることはないのに、周囲と別な考え方や習慣を持つ個人や家族は「村八分」となって、集団から排除されるのです。これが近代社会において国家規模まで拡大された結果が、昭和10年代ならファシストでない人間は我が国の国民にあらず、昭和20年代ならデモクラートでなければ人にあらず、という風潮なのです。ここでは、主張の内容は一切問題にされません、時代の風潮と、周囲の集団と、歩調を合わせているかどうかだけが問われるのです。 共産主義者を例にとってみましょう。戦時中の共産主義者は「非国民」でしたが、戦後になると「英雄」とされ、1990年代のソ連の崩壊後は「滑稽な道化師」になりました。しかし、たかだか人の一生の間に、ひとつの思想の意味がこれほど何度も変わるというのは、本来あり得ないことです。 判断停止も、付和雷同も、人格の一貫性に反することは言うまでもないことでしょう。 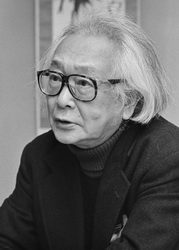 中村眞一郎 さて、今回取り上げるのは中村眞一郎の小説「回転木馬」です。 中村眞一郎は、野間宏や安部公房、花田清輝、福永武彦といったひとたちとともに、「戦後派」と呼ばれた作家です。ネルヴァルの翻訳や「源氏物語」をはじめとする王朝文学、江戸漢詩人の評伝なども書いています。あと、意外なところで、1961年の東宝映画「モスラ」は、原作が中村眞一郎、福永武彦、堀田善衛の3人によるものですね。 中村眞一郎は私の好きな作家です。小説ももちろんいいのですが、エッセイ・評論などでは自分の文学遍歴、比較文学論から文化論に至るまで、繰り返し語られていて、生涯文学創造への努力を怠らなかったひとです。これこそ、真に尊敬すべき、ほんものの知性だと思います。じつを言うと、私がプルーストやネルヴァルを読んだのも、「源氏物語」に親しんだのもこのひとの本による影響でした。 私は長篇小説好きなので、とくに好きなのは、「四季」四部作(「四季」「夏」「秋」「冬」)。これは、プルーストの「失われた時を求めて」に匹敵する、戦後に我が国で書かれた文学作品の最高傑作ではないでしょうか。晩年の「四重奏」四部作(「仮面と欲望」「時間の迷路」「魂の暴力」「陽のあたる地獄」)もいいですね。 「回転木馬」は昭和32年の刊行。物語の時点はこの時期と見ていいでしょう。こんな小説です― かつて戦時中の学生時代に「人類の未来の会」という名のもとに、哲学や芸術・文学を語り合い、平等な世界国家の建設に一生を捧げようと決意した仲間たちがいた。いま、彼らは成人しておよそ20年ぶりに東京で再会する。 そのひとり、鈴木はこの会に臨んで、若き日から捨てることのなかった文学の夢―自作の長編小説の原稿を持参し、いまや流行作家となったかつての友に託し、どこかの出版社に紹介してくれることを期待している。 ところが会のほかのメンバーたちは、昔とはすっかり違った人間に「成人」していた。大学の助教授となった男は妹の金の無心に苛立ち、町会議員となった男は雄弁に自分の町政についての抱負を語り、流行作家となった男はその日の晩に訪ねてくる女性のことを考え、鈴木の原稿を預かることを拒否する。それぞれが、輝かしかったはずの過去とは絶縁して、むしろその思い出を憎悪をもって否定しようとさえしていた。鈴木は失望するとともに、青臭いまま成長していない自分の滑稽さを自覚する。しかし、家に帰れば、自分の帰りを待っている妻、初枝が、やさしく迎えてくれるだろう・・・。 「人類の未来の会」に参加していた頃、初枝はこの会の指導者ともいうべき立場にあった曳馬という青年と恋人同士であり、「ディオチーマ」という渾名で呼ばれていた。星空のしたを並んで歩きながら、彼女はヘルダーリンの詩を暗唱し、未来への希望に酔い、幸福感に満たされていた。曳馬もまたヘルダーリンの詩の一節を口にした― 「神々の腕のなかで、私は成人した」 彼女は、その後出征した曳馬の戦死公報が出たため、疎開先で再会した鈴木と暮らすようになり、結婚したのだった。 ところが夫鈴木の留守中、初枝はかつての恋人曳馬の消息を耳にする。曳馬は戦死したのではなく、下半身が不随となって戦場から戻り、弟夫婦の家で寝たきりの生活、食事も排便も、いっさいを弟夫婦の世話になっている厄介者となり果てていた。 そして深夜、鈴木が帰宅したとき、初枝は縊死していた―。 かつて曳馬であったその男はいま、闇のなかで、陰鬱な諦めのうちに目を覚ます。そこに隣室の弟夫婦の会話が漏れ聞こえてくる。近くに住む分家の当主が旅先で発見した女性の話―彼は初枝という名を耳にする。長らく忘れていた少女時代の彼女の面影と、「人類の未来の会」の思い出がよみがえってくる。 感覚のない、身動きのできない身体が下痢をして、下半身を糞まみれにしながら、彼は無意識のうちに呟く― 「神々の腕のなかで、私は成人した」  Johann Christian Friedrich Holderlin ヘルダーリンについて説明しておきましょう。ヘルダーリンはドイツ古典主義とロマン主義の狭間に位置する詩人です。代表作はやはり「ヒュペーリオン」でしょうか。これもまた、ドイツ教養小説に分類することのできる、近代ギリシアの青年ヒュペーリオンの自己形成の物語です。ヒュペーリオンは純粋に精神的な愛で結ばれているディオティーマ残して、自らの理想と祖国のために軍隊に加わるのですが、しかし戦勝の喜びもつかの間、自分の軍隊が略奪行為を行い、同胞をも苦しめている現実に失望して、軍隊を離れます。やがてディオティーマの訃報がもたらされ、彼女の最後の手紙には、母なる自然の全一のなかに、別離を超えて抱きとられる自分たちであることがしたためられている。ひとり故国に帰ったヒュペーリオンの前には、ただ自然が広がっている。彼は、ディオティーマもまた抱き取られているであろう自然に帰一して、己が傷を癒やそうとする・・・。ここに、古代ギリシアへの憧憬と同時に、民衆の教育者たらんとするヒュペーリオン、ひいてはヘルダーリン自身の願いがこめられているのですね。 ディオティーマはヘルダーリンが家庭教師として入っていたフランクフルトの銀行家ゴンタルト家の夫人ズゼッテがモデルとされています。家の主人の邪推を買って、職を辞さねばならなくなったヘルダーリンの、ドイツ人を愛するが故のドイツ人批判・攻撃はいかにも時代を感じさせるところでもあります。 シュティフターの「晩夏」同様、現代人にはこのような気高い理想を歌いあげる文学作品はちょっとなじみにくいかもしれません。よく言われることに、「ヒュペーリオン」の幼児性があります。つまり、子供の純粋さがこの作品だけでなくドイツ文学の特性となっているということ。その意味では、ヘルダーリンなんて十代の若いうちに、一度は読んでおいた方がいいのかもしれしれません。 ・・・が、その皮肉がこの中村眞一郎の「回転木馬」なのです。眼前には前途洋々たる未来が広がっており、理想に燃える若者にはそれしか見えない。そうした若者たちの行く末を描いた、皮肉な青春の物語です。 (Hoffmann) 引用文献・参考文献 「回転木馬」 中村眞一郎 講談社 ※ 私の持っている昭和32年の初版本は旧漢字・旧仮名遣いです。 中村真一郎「人生を愛するには」 中村眞一郎 文藝春秋社 中村真一郎「愛と美と文学」 中村眞一郎 岩波新書 Diskussion Kundry:みなさん、今度から私のことを「ディオティーマ」と呼ぶことにしませんか?(笑) Parsifal:我々はもう、世俗の垢にまみれてしまっているからなあ・・・(笑) Hoffmann:「匂いフェチ」を自称するディオティーマってのも想像したくない(笑) Klingsol:そこは、人間の人格は統一的に一貫したものではないから許そうよ(笑) Kundry:全員の発言の語尾に「(笑)」がぶらさがったのは、はじめてですね。 Parsifal:中村眞一郎はHoffmann君の好きな作家だよね。 Hoffmann:単に「好き」ではすまされないくらいだよ。計り知れない恩義を感じないではいられないね。個人的には、ノーベル文学賞なんて、この中村眞一郎に与えなかったことで、賞それ自体が価値を失ってしまったと思っているよ。いま、我が国で候補に挙がっているのいないのと、根拠もなく取り沙汰されているくだらない自意識の汚物のような小説家がいるじゃない? あれが受賞すればいいんだよ。そうすれば、次回からノーベル文学賞なんてだれも見向きもしなくなる(笑) Kundry:またそんなことを(笑)以前、安部公房についても同じことをおっしゃっていませんでしたっけ。 Klingsol:しかし・・人間の人格が統一的に一貫したものではないという認識は、絶望につながるのか、諦念につながるのか、それともまだ希望はあるのか・・・・。 Hoffmann:難しいよね。とくに我が国では「亡命」の伝統がないからね。自分や家族を養うために収入の道を確保しなければならないのだから、やむを得ないこととも言えるし。 Kundry:ひとつ、質問があります。前回のマックス・ピカートのお話の際には、たとえばバッハやモーツアルトの音楽について、その感動を個人の行動とは別なところで真実のものと認めることができるといったお考えでしたが、文学、たとえばヘルダーリンやこの中村眞一郎の作品についても同じようにお考えですか? Hoffmann:そこが苦しいんだよね。音楽の場合は個人の人格や思想を超えたところ、根源的なところに訴えかけてくる作用を認めることができると思う。メンゲルベルクの「マタイ受難曲」に感動できるのも、思想や理屈ではないんだ。 Klingsol:ショーペンパウアーにならえば、音楽はイデアの諸段階で言うところの「意志それ自体の模写」であるということになるからね。鑑賞する側が、思想なんてものを超えた純粋な認識主観となっているというわけだ。 Hoffmann:ところが、たとえばヘルダーリンに関しても、同じことが言えるとは・・・なかなか考えにくい。 Parsifal:書いている側、表現する側にしてみれば、明確なメッセージがあるわけだからね。とくにドイツの作家は思想・哲学の伝達を目指している。 Hoffmann:よく、なんでもかんでも「時代の鏡」なんて言う人、いるじゃない? あれは「逃げ」だよね。他人事にしてしまって、自分で直接対峙してみることを避けているわけだ。もっとひどいのが、なんでも「好みの問題」にしてしまう人。単なる思考停止だよね。 Kundry:前回のお話に出てきたヴィスコンティの映画「ベニスに死す」だって、あれをホモ映画だと思っている人がいますからね(笑) Parsifal:ちょっと信じがたいほど、読み間違えたり、見間違えたりするワカランチンというのは、いるものだ(笑) Kundry:そんなのまで、「好みの問題」で片付けては、たしかに思考停止ですね。 Hoffmann:そう考えると、文学の場合は、そこで得た糧を人生で実践できないのは、やはり問題なのではないかと、考えられるんだよ・・・。 Parsifal:うん。と、すると・・・。 Hoffmann:ところがそこに、「人間の人格は統一的に一貫したものではない」・・・という事実が立ち塞がるわけだ。 Kundry:はは~ん・・・円環を描きましたね。 Klingsol:まるでニーチェだ(笑) |