153 「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」(「ポオ小説全集 II」) エドガー・アランポオ 大西尹明訳 創元推理文庫 「狂気の山脈にて」(「ラヴクラフト全集 4」) ハワード・フィリップス・ラヴクラフト 大瀧啓裕訳 創元推理文庫 「氷のスフィンクス」 ジュール・ヴェルヌ 古田幸男訳 集英社文庫 「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」 エドガー・アラン・ポオ 大西尹明訳 「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」は1838年に刊行されたエドガー・アラン・ポオの冒険小説です。ポオとしては唯一の長篇小説ですが、未完とも受け取れるような曖昧な結末になっています。 一応あらすじを説明しておくと― 物語は雑誌に掲載されたアーサー・ゴードン・ピムの冒険物語という体裁をとっています。 アメリカ東海岸のナンタケット島出身のピムが、密航を企てて友人の父の船にひそかに乗りこむが、友人とともに船上の反乱事件に巻きこまれ、漂流することになる。ピムを密航に誘った友人を含めたほとんどの乗組員が死んでしまい、かろうじてピムとダーク・ピーターズの二人だけが生き残ってウィリアム・ガイ船長のジェイン号に救助される。ケルゲレン群島のクリスマス・ハーバーを出港したジェイン号は、ウィリアム・ガイ船長が躊躇したにもかかわらず、ピムの強い勧めで南極へと乗り出して行く。 流氷群を越えた向こうには氷のない海が広がっていた。そこには見たこともない動物や植物、鉱物が存在した。また、氷のない南極の島には「白いもの」を極度に怖がる原住民が住んでおり、ウィリアム・ガイ船長の一行はその原住民の罠にはまって全滅。再びピムとダーク・ピーターズだけが生き残る。ふたりを乗せたカヌーは、天から流れ落ちる白い水蒸気の滝のなかへと進んでいく。その滝の裂け目からは巨大な「屍衣を着た人間のような」姿が見えて、ピムとダーク・ピーターズを乗せたカヌーはそこへ引き寄せられていく・・・ここで物語は終わる。 残りの数章は校訂のためにピムの手許に置いてあったが、突然の死去(自殺)のため紛失、発見されればいずれ出版されることになるであろうとされています。 この小説を読むと不思議な思いにとらわれます。ポオはなにを書こうとしたのか―波瀾万丈の海洋冒険小説でしょうか。そうかもしれません。ピムはまず密航者になり海に出る。後は事件の連続です。叛乱、嵐による難破、疫病船の出現と友人の死。貿易船による救助、野蛮な黒人の島に逗留して、黒人の裏切り行為によってカヌーで脱出、そして不可解な幕切れ・・・。ポオお馴染みの狭い空間での幽閉も描かれていれば、暴力的な死、腐敗、それにカニバリズムも描かれており、まるでスティーヴンソンの悪夢版のようです。それがリアリズムをもって迫ってくるのは、同様な筆致で書かれているのが、積荷の積載方法や陸亀やペンギンなどの生態にまで及んでいるため。 多くの批評家はそのリアリズムに反して、象徴的な物語ととらえているようです。白いものを極度に恐れる黒人が登場するのは奴隷制度に対する肯定的な態度を示し、いかにもアメリカの19世紀人の悪夢になっていると―。また、密航者であるピムは船倉の闇から再生して、氾濫や嵐、難破を経験して、ようやく人生の真の冒険へと歩み出す、という解釈も可能でしょう。 黒人の島「ツァラル」"Tsalal"は「暗くなる」という意味のヘブライ語、村の名前「クロック=クロック」"Klock-Klock"もヘブライ語で「だます」意、黒人の「ヌ=ヌ」"Nu-Nu"は「否定する」・・・このようないかにもポオらしい、悪ふざけ的なことばの遊びは、たしかにこの小説を風刺的あるいは象徴的な物語と思わせる要素になっています。 それでは「屍衣を着た人間のような」ものの正体はなんだったのでしょうか。これは物語の唐突な中断によって明かされてはいませんが、別に氷山がそう見えただけでもなんでも差し支えないんですよ。ピムにとって新しい世界が眼前に現れたということが重要なのです。狭くて暗い船倉(子宮)から出てきて、そこは海(羊水)ですからね、おまけに念の入ったことに、ラストシーンはカヌー、すなわち「うつぼ舟」で大洋を漂流中です。この物語の最後に目にしたものは、死と再生の末に認識したもの、すなわち再生の完結・完了なんですよ。屍衣というのも、もうポオの小説ではお馴染みのものでしょう。ポオの小説で屍衣を着た人間がおとなしく死んでいた例がありますか? みんな甦っているじゃないですか。そう思えば、この海洋冒険小説(として、おそらく書きはじめられたのであろう物語)も、ポオのいつもの流れに回帰しているんですよ。 (Kundry) ************************* 「狂気の山脈にて」 ハワード・フィリップス・ラヴクラフト 大瀧啓裕訳 「狂気の山脈にて」はハワード・フィリップス・ラヴクラフトの小説。これはポオの「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」の影響下に執筆されたもので、一部をその設定に取り込んでいます。そしてポオと同じく、ラヴクラフトにとってもめずらしい長編小説です。物語は地質学者ウィリアム・ダイアーの一人称視点で書かれ、彼の手記という体裁。 あらすじは― 1930年、ミスカトニック大学のウィリアム・ダイアー教授は、探検隊を率いて南極大陸へ向かう。目的は地下の岩石や土砂を採取すること。作業は順調に進み、ある地点では古生物の化石も発見される。しかし、生物学者のレイク教授は古い粘板岩上の奇妙な縞模様のほうに注目する。レイクは計画の変更を強硬に主張し、分隊を率いて地層が伸びる方角へ向かう。 やがて分隊からの無線通信で、未知の巨大な山脈に到達し、その地下洞窟から奇怪な化石を発掘した旨の報告を受ける。それは独自の進化を遂げた大型の生物で、「ネクロノミコン」に記された神話上の「古のもの」を連想させるものであると―。 しかし翌朝、決められた時刻になっても分隊からの無線連絡がない。ダイアーは最悪の事態を想定し、捜索に向かう。そこで発見し、体験したものは・・・彼は帰還すると、レイクの分隊は強風で全滅し、すべては失われたと嘘の報告をして、以後沈黙を守ることとなる。 1931年2月から3月22日にかけて執筆されたもの。10歳の頃から南極に心惹かれていたラヴクラフトが、推敲に推敲を重ねた自信作でしたが、「ウィアード・テイルズ」編集長からは「長すぎる」として掲載を拒否され、結局友人の尽力もあって、雑誌「アスタウンディング・ストーリイズ」1936年2月号から4月号にかけて分載されました。 ここでは、同じ南極大陸を舞台にしたエドガー・アラン・ポオの「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」についての言及もあり、借用された設定は、たとえば、ショゴスの鳴き声などがそうです。 "Tekeli-li ! Tekeli-li !" 原文で読めば、この小説全篇の、最後の一語ですからね。 「狂気の山脈にて」は、後に「クトゥルー神話」と呼ばれることになるラヴクラフト創造の超古代の地球の支配者の歴史譚が描かれた作品なのです。 ここで念のため「クトゥルー(クトゥルフ)神話」について説明しておくと、もともとラヴクラフトははじめから綿密な設定を練り上げていたわけではなく、ラヴクラフト以外の、友人や後継者となる作家たちによって成立していったものです。そもそも「クトゥルー神話」という命名からして、ラヴクラフトによるものではありません。 ラヴクラフトが考えていたのは次のようなものです―人類が現れるよりもはるか以前に宇宙から飛来して、地球を支配していた存在がある。彼らは地球上の表舞台からは姿を消したが、いまも海底や人跡未到の地、次元の狭間などに身を隠して、復活の機会をうかがっている。そして太古から彼らをあがめる秘密の教団も存在している・・・。 これがはっきりと提示されたのは「クトゥルーの呼び声」です。以後、「ダンウィッチの怪」「インスマスを覆う影」「闇に囁くもの」、さらにこの「狂気の山脈にて」「時間からの影」と書き継がれていきました。興味深いことは、「大いなる古きものたち(旧支配者)」"The Grest Old Ones"が、「クトゥルーの呼び声」ではその身体が物質でできてはいないとされ、「狂気の山脈」では強靱な肉体を持っているらしいこと。また、「クトゥルーの呼び声」ではひたすら悪意を持って世界を破壊するような存在として認識されているのですが、「狂気の山脈にて」では高度な知性を持ち、芸術を愛する生物であるらしいことです。この点については、「時間からの影においても同様の描き方がされています。これはラヴクラフトの「うっかり」というよりも、世界観を生成してゆく過程でそのような細部にはあまりこだわらなかったということでしょう。 やはり「狂気の山脈にて」と「時間からの影」を読むと、ラヴクラフトの原神話が、いかにも「神話」にふさわしい原型(元型)を備えていることが分かります。オーガスト・ダーレスをはじめとする後継の作家たちがこれを発展させたくなった気持ちも理解できますが、その発展形たる「クトゥルー神話」は、対する人間が知恵と勇気で闘うヒーローのように扱われたりしており、善悪の区分などが単純かつわかりやすすぎて、かえって原神話のスケールが大きいものであったと感じられます。 (Parsifal) ************************* 「氷のスフィンクス」 ジュール・ヴェルヌ 古田幸男訳 集英社文庫 未完のまま終わったかのように見えるポオの小説を完結させたのが、ジュール・ヴェルヌです。作品は「氷のスフィンクス」。 そもそもポオの「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」は、語り手がポオとピムと、最後のノートを書いたもうひとりの人物の3人です。つまり、語り手として自らの体験を語るピム、その体験をもとに小説を書くポオ、さらにもうひとり、ピムとポオの物語を解説する人間がいる。 深読みすれば、ポオの物語では、ピムもポオも、そのいずれもが物語の語り手であり、同時に作中の登場人物であるわけです。そこでヴェルヌはピムもその物語の登場人物も実在の人物であるという設定で続編を書いています。ピムもポオも、ウィリアム・ガイ船長もダーク・ピーターズも実在する世界で、「氷のスフィンクス」のstoryが展開されるわけです。 ここでヴェルヌは、ピムはじっさいには帰還しておらず、ポオにピムの手記をもたらしたのは同行者のダーク・ピーターズであるとしてます。だからピムの物語は「ノンフィクション」でありながら、そこには虚偽や不完全な情報が混じりこんでいる可能性を示唆しています。さらに、情報提供者ダーク・ピーターズも登場して重要な役割を果たします。 語り手はアメリカ人博物学者のジョーリング。彼がケルゲレン群島で遠洋航海船を待っていると、やって来たのはリヴァプール出身のレン・ガイ船長に率いられたイギリス船、ハルブレイン号。レン・ガイ船長はポオの小説に書かれている出来事はすべて事実であると主張。このレン・ガイ船長というのはピムを救出したジェイン・ガイ号の船長の弟。彼はポオの小説、というよりもピムの手記を検討して、兄のガイ船長と少なくとも5人の仲間たちは生存の可能性があると考え、捜索と救出を自らの任務としていた。 また、この船にはハントと名乗る人物が乗っており、じつはこの男の正体こそピムとともに生き残ったピーターズ。そして、帰国したのは自分だけで、ピムの手記をポオに渡したのは自分であり、ピムは死んでおらず、南極海の彼方にいるはずであると主張する・・・。 ポオの「ピム」が発表されたとき(1837~38年)にはヴェルヌは10歳くらい。翌年(1839年)に少年ヴェルヌは家出して遠洋航海の船に乗り込むという密航事件を起こしているんですよね。もっともヴェルヌの場合は父親に追いつかれて連れ戻されているんですが。ヴェルヌは晩年に至って、少年時代におそらく読んだであろうポオの小説の続編を書いたということになるんですね。 続編とはいってもそこはヴェルヌですからね。南極の果てに、「ピム」で描かれたような異界は存在しません。火山活動に伴う大地震で、めずらしい動植物も原住民もすべて失われてしまったということになっています。おまけにピムが南極点附近で見た異様な情景は幻として解釈されている。その代わりというわけでもないのでしょうけれど、同じ南極点に20年後にノーチラス号のネモ船長がやってくるという註釈がついています。 ダーク・ピーターズはポオの小説とはかなり異なった人物で、ひたすらまじめで、性格の暗いタイプになっている。これはポオの小説でも描かれていた人肉食事件のもたらしたトラウマということになっています。 また、ヴェルヌはポオの小説におけるピムの自殺事件という顛末を否定、その後のピムの物語を別に用意しています。これによると、ピムはしばしばヴェルヌが描いた冒険者たちと共通する人物で、すなわち神に挑んで返り討ちに遭うひとり。このあたりが、ヴェルヌがポオの「ピム」に目をつけた理由なのかも知れません。自分が書いてきた物語と共通するテーマを適用できると。人間の神への挑戦と、その成果、そして払わなければならない相応の代償。もうね、私はギリシア悲劇で言うところの「ヒュブリス」ということばを思い出してしまいましたよ。 (Hoffmann) ************************* 地球空洞説について 地下世界への旅は、古くは冥界探訪物語にはじまるわけですが、地下への旅と帰還は隠喩としては死と再生です。また、薔薇十字思想などに基づくオカルティズム秘密結社の秘儀参入儀式の象徴とされることもあります。文学ではオルフェウスの物語はもとより、ダンテの「神曲」の地獄遍歴も同様、ベックフォードの「ヴァテック」では主人公ヴァテックが魔王エプリスの領土を訪れていますね。 ポオの小説ではうっすらと匂わされているもの、そしてヴェルヌが「氷のスフィンクス」(1897年)よりも前に、「地底旅行」(1864年)ではっきり書いているのが「地球空洞説」です。この地球空洞説に基づく文学作品といえば、デンマークのルートヴィク・ホルベリ(ホルベルク)の「ニコラス・クリミウス(ニコラ・クリム)の地下世界への旅」がありますが、これはポオの「アッシャー家の崩壊」でロデリックと友人が読んでいますよね。じつはポオの「壜の中の手記」なども、地球空洞説を前提としていると言われています。しかし、ポオではその空洞になにがあるのかまでは言及されていない。いや、じつはその空洞に白人のユートピアがあったなんていう小説を書いた人はそれまでにもいたんですよ。19世紀後半でも、2018年に翻訳が出た、エドワード・ブルワー=リットンの「来るべき種族」(小澤正人訳 月曜社)あたりは地下世界に広がる理想社会を描いた、ユートピア小説としての地下世界旅行譚です。ところが、ヴェルヌではそこに古代の恐竜がいたという話になっています。「失われた世界」、すなわち「ロスト・ワールド」ですよ。地球内部の空洞の中に、「時間」を入れてしまったんです。 さすがヴェルヌは天才的、と思いますか。でも、考えてみればヴェルヌの冒険譚はイニシエイションinitiationですよね。しかも、地下世界なんて典型的な「胎内回帰願望」のあらわれです。いや、じつは海だって羊水ですからね。地球そのものが胎内回帰すればその地球の幼児期の記憶が再現されるのは、不思議でもなんでもない。「ロスト・ワールド」は地球にとっての失われた幼児期の記憶なんですよ。じつはポオの「ピム」の段階からして、アメリカという新世界から南極の果てへの空間的な移動は、母胎への遡行という時間的退行をはらんでいたわけです。水平動のようでいて、じつは下降なんです。もちろん、19世紀は古代生物、つまり恐竜の骨なんかが発見されて、個性生物学ブームがあったことも無視することはできません。また、(内面へと)ひたすら掘り下げてゆく、深く思考する・・・このあたりには、ロマン主義の精神の影響もあるのでしょう。 ここはもう少し説明が必要なところで、E・T・A・ホフマンは言うに及ばず、ゲーテやノヴァーリスにしても、当時の地質学の成果に大きく影響され、これがその思想に反映されているのです。とくに山に関しては17世紀末から論争がありました。つまり山は世界(地球)創世のはじめからあったのか、それともノアの洪水以降のカタストロフィーで地殻変動によって作り出されたものなのか、という論争です。当然、これは聖書解釈まで絡んでくる大問題。19世紀になると浸蝕と堆積による地殻形成説が主流となるわけですが、ロマン主義者たちを魅惑したのは、むしろカタストロフィー説であったわけです。火山の爆発や大洪水といった災害のimageが捨てきれなかった。そこに鉱物学的想像力も加わっていった。地球内部の空洞に「ロスト・ワールド」幻想を見たジュール・ヴェルヌが、無意識の「深層」に降下してゆく方法論を唱えたフロイトと同時代に生きていたことをお忘れなく。その降下が精神の地質学であり、時間遡行を実現するものであることも。 ただし、今回は地球空洞説についてお話しします。 地下世界というものの存在は古い神話・伝説でも示唆されていたところで、古くはデカルトの地球創生理論からアタナシウス・キルヒャーの、地殻内で両極をつないでいるという巨大水脈説もありますが、さしあたりエドモンド・ハレーが地球空洞説の草分けとみていいでしょう。 はっきりと「地球」の地下に「空洞」があると唱えられたのは、17世紀も終わりに近い1692年のこと。ハレー彗星の命名者として有名な天文学者エドモンド・ハレーが、あるエッセイの中で、地球は厚さ500マイル(800キロ)の殻を持つ中空の球体だという説を唱えました。その内部には、火星や金星と同じぐらいの大きさのふたつ内殻があり、中心には水星と同じぐらいの大きさの核がある。つまり多重球殻ですね。そのそれぞれの球の表面には生物が住むことができる、というのがハレーの論。さらに、そこから漏れてくる発光性ガスによって、揺らめくオーロラが生じるのだとも主張しています。 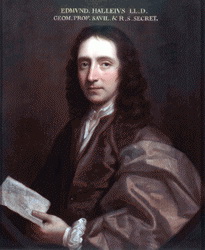  Edmond Halleyと空洞地球のモデル また、1818年、アメリカ陸軍の歩兵大尉ジョン・クリーブス・シムズは、「同心圏と極地の空洞帯」という本で、地球空洞説を唱えました。これによると、地球は厚さ800マイル (1,300km)、各々の両極に直径1400マイル (2,300km) の開口部を持つ五層の同心球で、地表の海はそのまま裏側にまでつづいているとされています。両極に開いた大穴から中に入っていけるはずだというのが彼の考え。シムズは自説を裏付けるために北極の探検行を計画し、「自分は精神病者ではない」という医師の診断書までつけた500部の趣意書を、アメリカやフランスの政界、財界、学者に配布したうえ、探検の資金を提供するよう国会にまで働きかけたものの、相手にされず、費用が集まらなかったため、この北極探検は頓挫しました。ただし、付け加えておくと1828年、ロシア皇帝から文書が届き、ロシア帝国主催の北極探険隊の隊長就任を要請されています。しかしシムズは1829年に死亡して、この計画には参加できませんでした。 このシムズの説は、初期の地球空洞説のなかではもっとも有名なものなので、その「趣意書」を引いておきましょう― 諸君! 余は地球の中味が空洞であり、内部に人間が住めるものであることを証明する。地球は幾重にも層をなす球体圏を内蔵しており、かつまた極地は12度から16度ほどぱっくりと口を開けているのである。余はこの説の証明のために生命を賭し、世人が余のくわだてに助力を惜しまないなら、この空洞の研究に身を捧げるであろう・・・ 余は完全装備せる一千人の勇敢なる同行者を募り、秋季にシベリアを出発してトナカイと橇により凍れる海の氷上を渉らんとするものである。余は保証するが、北緯62度の北西1度の位置に到達するならば、余等は青々たる草木と動物たちの犇めく、暖かい、豊かな国土を発見するであろう。成功の暁には、春季に帰還するであろう。   John Cleves Symmesと同心圏理論の図解 シムズの説の発表ののち、1820年にアダム・シーボーンなる人物が「シムゾニア」Symzoniaという本を書いていて、これによると船で地球内部に入り、シムズにちなんでシムゾニアと名付けたユートピア世界を訪れるという内容なんですが、この著者はじつはシムズ自身ではないかと考えられています。 ポオはシムズの説に関心を持って、まず書いたのが「ハンス・プファアルの無類の冒険」(1835年)、その次が「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」(1837~1838年)です。なので、もうすこし詳しく説明しておくと、地球内部には同心円の球体が重なっていて、ところどころ土塊でつながっている部分もある、この迷宮のような内部空間を植民すれば、領土拡張もたやすくできる・・・と、どうもここがいちばんのキモだったらしい。それでアメリカ全土を行脚して、いたるところで講演会を開催するも、山師の大法螺としか思われず(アタリマエダ・笑)、ついには合衆国議会にも二度にわたって自説の支持を求めたのですが、まるっきり相手にされず。 なお、シムズの墓には空洞地球の記念碑が建てられており、そこには「彼は、地球が空洞でその内部に人が住むことができると、あくまでも主張して譲らなかった」という、どことなく皮肉な調子の碑銘が刻まれているそうです。 とはいえ、上記趣意書の後の方、なかなか具体的な計画じゃないですか。当人としてはそれなりの確信を持って、計画を練っていたことが分かります。 シムズの理論によれば、地球内部の気体は地表のそれよりもやや希薄ながら、動物が生活を営むには十分、一方の極の穴から雲が降下してくるので、雨や雪も降る。台風も一方の穴から入ってもう一方に抜けていくので、空気は絶えず循環している。空洞各圏の光は地表ほど明るくはなく、温度もさほど高くはないが、それでも動植物が棲息不可能なほどではない。光源は希薄な水素ガス。そのほかに極地近くの深海の底から太陽光線が浸透してくることもあり得る。 その論拠のひとつは、北極近くの漁師や捕鯨船員が報告している鳥や動物の北上移棲、魚の極地圏移動などの目撃譚でした。そのように生物が移動した先には、必ずや気候温暖な国土が広がっているに違いないと―。 シムズは以上にして、もう少し続けましょう― シムズの活動からおよそ100年後の1913年、コルセット会社の機械保守の責任者だったマーシャル・B・ガードナーという男が、やはり地球空洞説を唱える本を出版。彼はシムズの同心球説を否定し、地球には最も外側の厚さ800マイル(1,300キロ)の殻しかなく、中心には直径600マイル(960キロ)の太陽があって、空洞の内側を照らしていると説きました。また彼はシムズと同様、両極には直径1,400マイル(2,300キロ)の大穴が開いているとも主張。オーロラというのはそこから外に洩れてくる光なのだ―と。 内部に太陽(光源・熱源)を持ってきたところがシムズとの大きな違いですね。さらにユニークなのは、我々の世界、つまり地球の外面での陸地は内部では海になり、表が海なら裏では陸地であるという主張です。これによると、地表の太陽の裏側には消えた大陸アトランティス、レムリア、ムーなどが「亡命」しており、そこにはいまもってマンモスなどの古生物が生存しているはずであると―。ガードナーによれば、極地探検家が報告しているシベリアの凍結されたマンモスの遺骸は、地球内部から氷河や氷山に梱包されて開口部付近で凍り付き、シベリアに押し流されてきたものである、ということになります。 じつはこのガードナーも、自らの仮説を立証するために極地探検を計画しているんですよ。エスキモーを何人か雇って、グリーンランドから犬橇で出発して、グリーンランド沿岸ぞいに北進すればいいと―。もちろん、この旅は想像上のもので終わりました。 シムズにしてもガードナーにしても、アメリカ合衆国市民であったことにご注目下さい。 古来から天上界にもっとも近い地上の楽園は、すべて北方の極地にあると想定されてきたのです。コロンブスは地球を横倒しに考えてしまったので、西へ行ってアメリカ大陸に到達したんです。でも西方の楽園というのはまったくの誤解。そこで、シムズやガードナーは地球像を旧に復して、ふたたび上、すなわち北極に世界山を夢見て船出しようとしたのです。楽園探求の夢なのです。 おもしろいのは、アメリカ先住民族たるインディアンの間には、彼らの祖先が巨大な島の空洞に住んでいたという伝承があるのです。また、ガードナーがエスキモーを雇うことを思い立ったのも、エスキモーたちは、自分たちの祖先が「四六時中光のある地球内部」からやって来たという神話を持っているから。 旧大陸の清教徒たちは新大陸にやって来て、アングロ・サクソン人種は政治的にはアメリカを支配しました。しかし、道徳的にはインディアンから、生活様式の多くは黒人奴隷から甚大な影響を被った・・・とはカール・グスタフ・ユングの指摘するところです。だとすると、地球空洞説の珍妙な地球論も、被征服民族の神話・伝説の隔世遺伝だったのかもしれません。  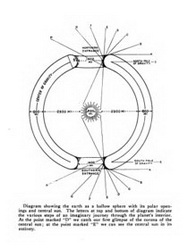 Marshall Blutcher Gardnerと極の開口部と中心の太陽が示された中空の地球の図 じっさいににそうした地球内部の世界に旅してきた(と主張する)人物もいるんですよ。 1908年に出版されたウィリス・ジョージ・エマーソンの「スモーキー・ゴッド」(邦題「地球内部を旅した男」五次元文庫)という本は、ノルウェー人の漁師オラフ・ヤンセンの手記を紹介しています。ヤンセンは父親とともに北の海から地球内部に入りこみ、親切な巨人たちに出会い、最後は南極の穴から出てきて、捕鯨船に救助されたというんですね。 また、1929年、リチャード・イヴリン・バード海軍少将が、航空機によって北極点上空を飛行した際、奇妙な世界に迷いこみ、広大な森林やマンモスを目撃したと言っています。後に発見されたバード少将の秘密の日記には、さらに驚くべきことに、1947年に南極を飛行した際にも地底世界に入りこみ、住人と接触していたとされている。 地球空洞説を証明する写真、これは以前にもHoffmann君がupしていましたが、いま一度ご覧に入れましょう。1968年11月23日、気象衛星エッサ7号が撮影した写真です。地球空洞説を唱える人たちによれば、ここには北極にある大きな黒い穴がはっきりと写っているではないか、というわけです。 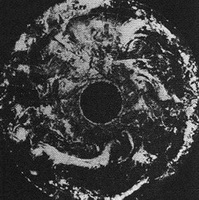 なんだかもう、真面目に反論するのもばかばかしいんですが・・・現代でも地球空洞説を主張する人の、その主張の内容は、ほとんどがガードナーあたりの受け売りです。その後の新しい知識は一切無視。なので、彼らの科学知識は100年ほど前の状態でストップしています。 地震波の伝わり方などを観測した結果、地球の内部がどうなっているかはとっくに分かっている。半径6,300キロの地球は、表面の地殻とその下のマントル層が固体、深さ2,900キロから5,150キロまでの外核が液体、5,150キロから中心までの内核が固体です。 考えてもみて下さいよ、そもそも、直径1万キロもの空洞など物理的に存在し得ないんですよ。地球はそれ自体の重力によって中心に向かって縮もうとしているんですよ。もしも地球が厚さ数百キロしかない空洞だったとしたら、その殻の重さは1平方メートルあたり1,200万トンになる。これを柱も壁もなしに空中に支えることなど無理筋。 また、そんな空洞がどうやってできたのか? 地球の内部にガスが発生して風船のように膨らんだとする主張がありますが、地球は薄いゴムではありません、あたりまえですけど(笑)1平方メートルあたり1,200万トンの重みに逆らうならば、最低でも120万気圧が必要になる計算。そんな気圧ではどんな気体も小さく圧縮されてしまいます。 仮に、そんな空洞があっても、内部は無重力になってその内側に人が立つことはできません、遠心力? それなら極付近ではどうですか? ましてや中心に太陽などがあれば引力で引っ張られて、中心に向かって落下していきます、そうなれば焼け死ぬだけのこと。 ウィリス・ジョージ・エマーソンの「スモーキー・ゴッド」は、いうまでもなくフィクション。バード少将の秘密の日記を持っていると主張したのは、ハーレイ・バードというバード少将の孫を自称する人物なんですが、じっさいは血縁関係はありませんでした。おまけに、自分を批判するUFO研究家に猥褻な手紙を送ったり、脅迫電話をかけたりしたあげく、公園で裸でいたところ、公然わいせつ罪で有罪判決を受けたという、どうも相当頭のおかしい男だったようです。ああ、お粗末(笑) 北極の大穴の写真については以前、Hoffmann君が「映画を観る117 「沖縄怪談 逆吊り幽霊/支那怪談 死棺破り」についてのお話しでふれていましたね。その時のコメントから引用しておきましょう― 地球空洞説といえば、これがはじめに提唱されたのは19世紀初頭、フランスとアメリカ、ほぼ同時です。このとき、アメリカで言いだしたのは陸軍大尉なんですが、その意図は領土拡張。合衆国議会に自説の支持を求めるも相手にされず。ところが、20世紀になってアメリカの気象衛星が撮影した、北極に真っ黒な穴が空いている写真で地球空洞説がまたまた話題になりました。その写真をご覧下さい。単にカメラのアングルの関係で写っていないだけだとする説もありますが、よく注意して見て下さいよ。地球一回り、全部日があたっている(昼間である)・・・ンなわけないでしょ。つまりこれは時間をおいて撮影した複数枚の写真を合成したもの。それでも北極周辺が真っ暗だということは、つまり日が昇らない極夜の季節の写真なんですよ。うっかり騙されちゃった人が、後に「穴があったら入りたい」と言ったかどうかは分かりません。 ついでに言っておくと、極軌道を周回する人工衛星はたくさんあります。アメリカやロシア、ヨーロッパ各国にも多数あり、日本の地球観測衛星にも複数あって、だいたい90分で地球を周回しており、一周するごとに北極の上も南極の上も通過しているんですよ。穴が空いていたら気付かないわけがありません。だいいち、南極点にはアメリカのアムンゼン・スコット基地があるし、いまではここを訪れるための観光ツアーもある。現代では飛行機もGPSを用いているので、地磁気の影響で航路が南極点から大きくズレるなどということもあり得ない。南極点にはいつも雲がかかっているというのも「見てきたような嘘」。夏はたいがい晴れ渡っています。 地球内部からのオーロラというのもナンセンス。オーロラは太陽の荷電粒子が地球の磁気に引き寄せられて、大気にぶつかって発光するもの。太陽の活動が活発になると、極地以外でもオーロラが見られることがあるのはわりあいよく知られていること。国際宇宙ステーションから撮影したオーロラの写真を見てご覧なさい、どこに穴が空いていると言うんですか? 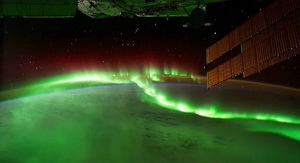  国際宇宙ステーションからとらえたオーロラ (Klingsol) 引用文献・参考文献 「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」(「ポオ小説全集 II」) エドガー・アランポオ 大西尹明訳 創元推理文庫 「狂気の山脈にて」(「ラヴクラフト全集 4」) ハワード・フィリップス・ラヴクラフト 大瀧啓裕訳 創元推理文庫 「氷のスフィンクス」 ジュール・ヴェルヌ 古田幸男訳 集英社文庫 「アナクロニズム」 種村季弘 河出文庫 「謎解き 超常現象 III」 ASIOS 彩図社(Kindle版) Diskussion Kundry:ラヴクラフトの「狂気の山脈にて」やヴェルヌの「氷のスフィンクス」を読むなら、ぜひともポオの「ピム」も読んでいただきたいということで・・・。 Parsifal:ラヴクラフト以上に、ヴェルヌの「氷のスフィンクス」を読むならポオは必読だよね。 Hoffmann:ポオの、ではなくてラヴクラフトの「狂気の山脈にて」に連なる系列では、いろいろあるなかで、コリン・ウィルソンに注目作があるね。 Kundry:以前、Parsifalさんが取りあげた「賢者の石」がクトゥルー神話作品でしたね。 Parsifal:コリン・ウィルソンによるクトゥルー神話系列の作品は、ほかに「精神寄生体」(小倉多加志訳 学研M文庫)、「ロイガーの復活」(団清二、すなわち荒俣宏訳 ハヤカワ文庫)もあったけど、南極大陸での発掘調査を描いているのは「古きものたちの墓」。扶桑社文庫から出ていたね。中篇程度の長さで、ラムジー・キャンベルとかブライアン・ラムレイの短篇も収録されている。文庫本の表題は「古きものたちの墓 クトゥルフ神話への招待」だ。ただ、コリン・ウィルソンだと、人間の意志力とか精神力で対抗できてしまうようなところがあって、ラヴクラフトのそれというよりは、オーガスト・ダーレスによる「神話」作品の末裔と見えるんだな。 Hoffmann:Klingsol君の話では地球空洞説の前提であるところの地下世界、ロスト・ワールド、精神への降下というのが重要なキーワードだね。 Klingsol:そのうえで、もう一度、ポオやラヴクラフト、ヴェルヌを読んで欲しいな。もっとも、ヴェルヌなら「地底旅行」の方がふさわしいか。ヴェルヌの「地底旅行」では、発端となったサクヌッセンムが16世紀の錬金術師であったとされていることに注目したいね。 Hoffmann:地下世界に降りてゆく物語は、古来から世界中に広く見られるからね。ギリシア神話はもちろん、我が国の「黄泉の国」もそうだし。カール・ケレーニイは「迷宮、地下構造物、冥府は死の観念の表現形式」だと言っている。それを再発見したのがゴシック・ロマンスだ。つまり、地下は死の世界、死の空間なんだよ。 Kundry:宮崎駿監督の「ルパン三世 カリオストロの城」(1979年)などはそのゴシック・ロマンスの末裔ですよね。道具立てばかりでなく、なにしろカリオストロ伯爵とその一味が「ゴート族」の末裔という設定で、彼らが造幣している偽札が「ゴート札」と呼ばれているんですから。 Parsifal:念の入ったことだ(笑) Kundry:ヒロインのクラリスはローマ文化を象徴しているんですよ。つまり、ローマとゴートの敵対関係をそのまま下敷きにしているんです。 Hoffmann:そして、地下世界に囚われの乙女がいるわけだ。「囚われの乙女」っていうのは、必ず塔か地下か、そのどちらかに幽閉されている。塔はともかく、地下に幽閉されているということは、無意識下の抑圧だろう。洞窟なんかも同じだ。 Parsifal:洞窟となると、古代ギリシアの神託所とか、初期キリスト教のマリア信仰と結びついているよね。 Klingsol:冥界であると同時に、万物が生まれ出る母胎でもあるんだよ。死と再生だ。錬金術師が関わってくるのも理の当然だね。そうした精神的背景があったところに、19世紀に発掘調査がすすんで、地質学、古生物学、考古学が発達した。これは同時に歴史の探究でもある。歴史の遡及、すなわちタイム・トラベルだよ。だから今回取り上げたヴェルヌやラヴクラフトの小説のように、地下に古代生物や「古きものたち」が見出されることになる・・・。 |