168 「血みどろの入江」 "Ecologia del delitto" (1971年 伊) マリオ・バーヴァ 英題なのか、"A Bay of Blood"と表記されますが、イタリア語原題は「犯罪生態学」の意。  あらすじは― 海辺の屋敷。フィリッポ・ドナティ伯爵は湾岸地区の開発を計画する建築家フランコ・ヴェンチューラとその秘書ラウラと結託して、開発に反対する自らの夫人フェデリカを自殺と見せかけて殺害するも、当人も変死を遂げる。そしてその伯爵の死体を発見した若者グループも殺される。 伯爵令嬢レナータは母親の「自殺」と父親の「失踪」の謎を解くべく、夫アルベルトとともに湾岸地区を訪れ、伯爵邸の近くに住む生態学者パオロ・フォッザッティとその夫人アンナを訪問し、母親の産んだ私生児である地元の漁師シモーネの存在を知る・・・。 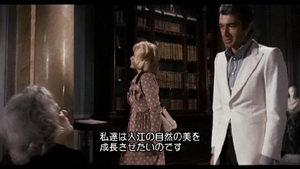 マリオ・バーヴァというと、インタビューで結構過激な発言、ふて腐れたような自嘲的な発言をしていたためか、強面のimageを持たれていたようですね。ところが、じっさいは楽天的で冗談好き。息子のランベルト・バーヴァによれば、「父は自分がすぐれた監督だと自負していた」とのこと。自嘲的な発言は、イタリアにおけるホラー映画の地位の低さ故だったのでしょう。 マリオ・バーヴァの父親は画家兼彫刻家で、映画の撮影隊に小道具を提供したことから、黎明期のイタリア映画に深く関わった人。マリオは青年期には漫画家を志すも、やがて父親の後を継いで映画界入り。はじめは特殊効果を担当して、後に撮影マンに。演出家デビューは名作「血ぬられた墓標」"Black Sunday"(1960年 伊)。これは、ハマー・フィルムのテレンス・フィッシャー監督による「吸血鬼ドラキュラ」"Dracula"(1958年 英)を観て、自分ならもっと上手く撮れると考えて取り組んだとも、たいして乗り気でなく請け負った仕事だったとも言われています。そしてこの作品がアメリカで大ヒット。次々と持ち込まれるホラー企画をこなすうちに、恐怖映画の巨匠となりました。 ところが人物としては敬虔で蠅を殺すのも嫌がり、運命論者で、自宅でひとり就寝する際には、必ずベッドの下を確認するという怖がり屋さん。 晩年は監督した作品の編集中に制作者が破産して、撮った映画がお蔵入りになるなど、不運に見舞われ、66歳で没。  マリオ・バーヴァが監督・脚本・撮影を務めた作品にして、周囲に与えた影響も大なるものがありながら、なぜかマリオ・バーヴァについて語るときに、この作品に言及されることが少ないような気がするんですが・・・。 本作はジャッロ映画の流れにある作品とされることもあり、スラッシャー映画の先駆けとされることもあれば、マリオ・バーヴァが監督・脚本・撮影を務めた本格的なスプラッター映画と言われることもあります。たしかにジャッロと言えばジャッロだし、84分間に13人を血祭りに上げるスラッシャーの草分けとも言えそう。全篇にわたって血みどろですからスプラッターと言ってもおかしくない。つまり、この1971年に公開された映画、それだけ影響力が大きかったということ。残酷描写と映像美は無論のこと、storyの構築も巧みです。「13日の金曜日」が、この映画にインスパイアされて作られたことはよく知られていますよね。つまり、ホラー映画に与えた影響も大きい。  この作品は「13日の金曜日」シリーズのすべての要素を持っていて、同シリーズには欠けているスタイルも備えている、と称賛されることもしばしば。撮影は創意工夫に富んでいるが、脚本には難あり、とする評価も見られます。たしかに、惨殺に次ぐ惨殺は13人に及び、結末はなんとも皮肉なもの。これを「皮肉なジョークのよう」と評した人もいます。殺人鬼の正体を隠そうともせず、冒頭から殺していることをもって、反ジャッロ映画であって、そこがアメリカ映画の手本になったとする指摘は納得が出来ますね。水辺を舞台をしているのも、母親とその息子にまつわる連続殺人を描いているという点も、まさに「13日の金曜日」のモデルになっている。性交中のカップルの串刺し描写も「13日の金曜日 PART2」で模倣されているでしょ。だから、「血みどろの入江」という手本なしに「13日の金曜日」シリーズは存在し得ないと断言している人もいます。   マリオ・バーヴァの影響力と言えば、オムニバス作品「世にも怪奇な物語」"Histoires Extraordinaires"(1967年 仏・伊)のフェリーニによる第三話「トビーダミット」には、マリオ・バーヴァの「呪いの館」"Kill Baby... Kill!"(1966年 伊)から、白い鞠を持った少女が引用されていましたよね。 バーヴァの作品の最大の特徴は「格調高さ」ではないでしょうか。たとえば「血ぬられた墓標」はモノクロながら残虐なショック映像で、サスペンスを盛り上げ、怪奇味も幻想味も、加えて映像美も備えた名作です。ショック演出にも事欠かないんですが、どこかエレガント。エロティックな要素を散りばめて下世話なテーマを展開しても、煽情的なだけではない品位を保っているのがマリオ・バーヴァなんです。カラーの時代になるとグリーンやレッドの照明で陰影豊かな映像を作りあげ、猥雑でありながら、雰囲気描写の巧みさで格調高くなるのは、これは天性の才能じゃないでしょうか。際物が際物に見えないんですよ。私は、ダリオ・アルジェントは「サスペリア」の色遣いにおいて、アルジェント当人が言っているディズニー映画よりも、じつはマリオ・バーヴァのカラー作品をお手本にしたのではないかという気がしています。さらに、水泳中の女性が腐乱死体に遭遇するのはバーヴァ本人の協力の下に制作された「インフェルノ」が模倣していますよね。また、「スタンダール・シンドローム」"La sindrome di Stendhal"(1996年 伊)などは、その主要な骨格をバーヴァの「白い肌に狂う鞭」"La frusta e il corpo"(1963年 伊・仏)から「いただいて」います。しかし、ダリオ・アルジェントと大きく異なるのは、バーヴァには皮肉とブラック・ユーモアがあって、殺人は単なる殺人ではなくて、人間の非人間化であるということです。だから、どことなく上品になる。反面、このこととトレードオフに倒錯性は希薄です。  この「血みどろの入江」ではひとりの殺人鬼が大暴れ・・・ではなく、殺し合いという展開もユニーク。どことなく、哀愁漂う雰囲気もマリオ・バーヴァらしいところ。もともとは女優のラウラ・ベッティが、マリオ・バーヴァと夕食をとりながら話している時に、この映画の案が出たと言われており、脚本はバーヴァがダルダーノ・サチェッティとともに完成させました。サチェッティは当時ダリオ・アルジェントの「わたしは目撃者」(1971年 伊)で注目されはじめたばかりの新鋭。主演は「007 / サンダーボール作戦」"Thunderball"(1965年 英・米)のボンドガールとして名を馳せたクローディーヌ・オージェなんですが、その他の登場人物が添えものになっておらず、それぞれに見せ場を持っているところも特徴のひとつです。そしてなんと言っても・・・cynicalな結末がいいですね。それを際立たせているのが、ステルヴィオ・チプリアーニの音楽です。  (Hoffmann) 参考文献 「ジャッロ映画の世界」 安井泰平 彩流社 「イタリアン・ホラーの密かな愉しみ 血ぬられたハッタリの美学」 山崎圭司編 フィルムアート社 「ホラーの逆襲 ジョン・カーペンターと絶対恐怖監督たち」 鷲巣義明編 フィルムアート社 |